卒業論文|研究テーマの選び方・向き合い方
読者のことも配慮した「楽しい論文」になるテーマを探そう
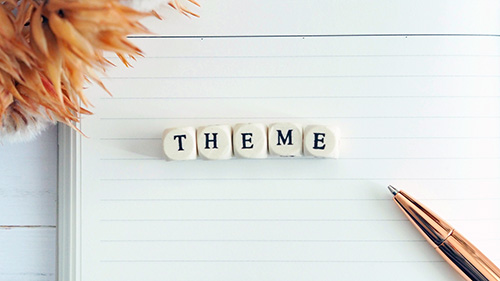
明確な問い(研究のポイント)が立てられ、論理性と形式が整っていることは学術論文に共通する最低要件です。でもそこに読者がいる以上は、「読んで楽しい」論文を目指してほしいものです。「書いて楽しい」「読んで楽しい」、おまけに指導教員も「教えて楽しい」論文。そんな「3方ヨシ」となるテーマを探しましょう。
本当に興味のある研究テーマかを自分に問いかける
卒業論文は、少なくとも2年以上にわたって向き合う大きな課題です。締切に追われて安易にテーマを決めてしまうと、途中で行き詰ってしまいます。学術的な観点からみたテーマの良し悪しや、書きやすさや書きにくさはあるにせよ、何より本当に自分が興味があるテーマか、わくわくして研究に取り組める内容であるかが大切です。
わくわくできるテーマに出会えると、研究は楽しくなります。最近の中学・高校では、研究テーマを設定した探求型の授業が実施されています。卒業論文の研究もそれに似ています。小学生の頃の「自由研究」のように、自分の興味や関心に基づいて、調べるたり眺めたりすること自体が楽しくなるようなテーマに出会えると毎日の研究は大いに捗ります。
ただし、卒論のテーマ決定においては、ワクワクする以前に「その研究の学術的意義」が問われます。単に「好きなテーマだから」「調べてみたいから」だけでは不十分。先行研究で手薄な部分があるとか、先輩方の研究をさらに検証する必要があるなど、何らかの学術的根拠を指導教員に説明できることも必要です。
研究テーマは「広すぎず狭すぎず」を心がける
私の英語スピーチ・プレゼンテーション研究室では、3年次の秋に研究テーマの提出と承認があり、4年次の春に論文タイトルを確定します。その研究テーマや論文タイトルは、一度提出すると変更できません。厳しいようですが、その分学生は真剣に自身の研究テーマと向き合いますし、計画的に研究を進められるようです。
学術研究は「狭く深く」が原則ですが、卒論の研究テーマを考えるときは「広すぎず狭すぎず」が理想的です。広すぎると何から研究を始めていいか自分でもわからないし、狭すぎると研究テーマが自分の関心とズレていたことに気づいたときに融通がききません。
「Steve Jobsの研究」「Deliveryの研究」はどれもそれらしいテーマですが、「Steve Jobsの研究」では広すぎて彼の何に焦点を当てたいのかが分かりません。「Deliveyの研究」についても、デリバリーの中には、ジェスチャーやアイコンタクト、姿勢、声など、広範な研究対象が含まれるので研究テーマとしてはもう少し絞った方が研究に取り組みやすいです。
たとえば、両者を組み合わせた「Steve JobsのDeliveryの研究」であれば、研究すべき範囲が適度に絞られていて、何から始めれば良いかがイメージできます。実際に研究を進めていき、タイトルを確定する際には「Steve Jobsの新製品プレゼンテーションにおけるジェスチャーの研究」といったピンポイントな論文タイトルに絞り込めるでしょう。
わくわくするテーマ選びの重要性はスピーチも卒論も同じ
テーマについては、指導教員としっかり相談しましょう。良いテーマが見つかると、その後の研究が楽しみになり、結果として読み手が「楽しく読める論文」に仕上がります。良いテーマが重要なのは、スピーチも卒業論文も同じ。信頼できる指導教員と相談を重ねつつ、自分が好きで、かつ書きやすいテーマを探してください。
目の前の研究に取り組んでいると、忘れがちなのが読者の存在です。指導教授を筆頭に、仲間のゼミ生との輪読など、多くの人があなたの卒業論文に目を通します。その時のために「楽しく読んでもらえる論文を書こう」という初心を忘れないでください。
論文指導教員として卒論を読んでいると、その研究が「わくわく」に満ちていたのか「苦難」の連続だったのかが読み取れるものです。読み手がワクワクして読める論文を書くためには、研究そのものがワクワクできないといけません。だからこそ、純粋に熱中できる研究テーマが必要なのです。
推理小説を読むような、謎解きと発見に満ちた論文を書くために、皆さんがユニークな研究テーマと出会えることを願っています。
▶ 関連記事:THE WISDOM 第23号 発刊 [リンク]

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など


