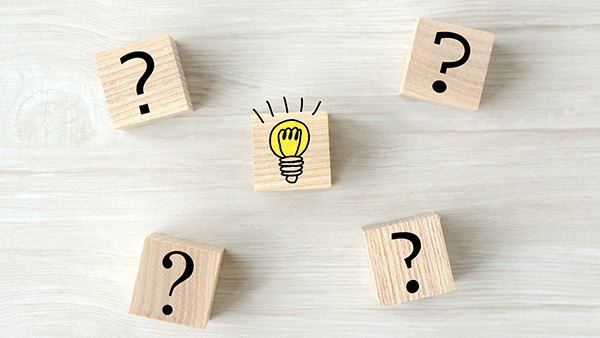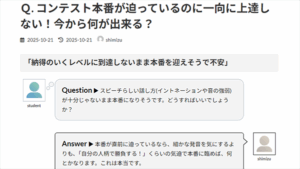スピーチ冒頭の疑問文「直球ど真ん中」から「暴投」までを見極めて指導する
冒頭での質問は、効果的なコントロールを意識する指導を。
※これは教員向け(教え方)の記事です。

英語スピーチは「疑問文で始めると効果的」という指導をされることが多いようです。その際の質問が、スピーチの核心的メッセージをどの程度反映しているかによって、イントロの雰囲気やスピーチのスピード感は大きく変わります。「ストライク直球ど真ん中」から「外角いっぱい」、さらには「暴投」まで、質問の立て方について教員目線で考えてみます。
質問の投げ方によってスピーチのスピード感は変化する
スピーチのオープニング部分で聴衆に質問を投げかけるのは、よく使われるテクニックです。あらゆるレベルの学習者を対象としたスピーチ指導で応用されますが、その際に考えたいのが「メインメッセージ」との関係性です。
冒頭の質問が「メインメッセージ」にがっちりとリンクしている場合、イントロは攻めの空気になります。いわば、「ストライクゾーン直球ど真ん中」の質問です。たとえば、「家族との食事を大切にしよう」がメインメッセージのスピーチで、冒頭に「最近、家族と食事をしていますか?」と問いかける質問がそれにあたります。
しかしこれが「夕食はいつも誰と食べますか?」となると、少しコントロールが外れてきます。それでも十分にストライクゾーンです。「昨日の夕食は誰と食べましたか?」はその変化球といったところ。メインテーマが「家族」と「食事」ですから、片方の「家族」がぼやけて「誰か」になるだけなら、まだまだ十分にストライクゾーンに入ります。
ストライクゾーンに入る疑問文から始めると、イントロ(introduction)の段落から、本題に向けて直球勝負のキレのある流れが生まれます。直球系の質問は、もたつきの無い、スピード感のあるオープニングを演出するには欠かせないテクニックです。その明快さから、初級者にも扱いやすい質問だといえます。
「外角いっぱい」の質問は緊張感を生む
さらに少し、コントロールを外してみましょう。「毎日の食事を楽しんでいますか?」であれば、食事の楽しさや団らんを連想させますので、ぎりぎり外角いっぱいストライクといった感覚です。「最近、外食が増えていませんか?」「外食はお好きですか?」も、まだ「家族」の話題へ簡単に誘導できることから、その変化球だと考えられます。
「外角いっぱい」の質問を投げると、聴衆は「何のための質問だろう」と勘を働かせる緊張感を感じるでしょう。うまく「食育や健康の話題かなあ」と聴衆に感じさせることができれば、家族との食事の大切さの一端に触れることのできる、まさに外角いっぱいのストライクになります。
さきほどの「直球ど真ん中」と違い、「外角いっぱい」の質問は、聴衆に少なからず「連想力」を求めます。言い換えれば、質問を処理するための労力が増えるため、イントロにおけるスピード感や「ピント」が曖昧になりやすいですから、それを意図してコントロールできる中級者向けのテクニックだといえます。
ボール球か「敬遠」か、はたまた「暴投」か。
残るはボール球です。メインメッセージに「かすってはいるけど外れている」質問です。たとえば「好きな食べ物は何ですか?」「最近、家族と出かけましたか?」あたりでしょうか。何とか「家族との食事」の話題に持って行けそうですが、そこまでにはいくつかの話題を経由する必要がありそうです。
このようなボール球を意図的に投げる、「敬遠」に似た質問のテクニックがあります。メインメッセージに少しだけ触れる質問をするのです。その代表例が「最近、家族の顔を見たのはいつですか?」「家族の趣味を知っていますか?」といった質問です。これらは、メインのメッセージに近いようで、遠い質問だといえます。
ここでいう「敬遠」は、聴衆の興味をじっくりと引きつけつつ、いくつかのステップを経て、「家族との食事」というメインメッセージにたどり着く面白さを作り出す効果があります。本論に向けて、聴衆の興味や関心を高めたい場合に、戦略的に用いる上級者向けの技術だといえるでしょう。
実際、「最近、家族の顔を見たのはいつですか?」「家族の趣味を知っていますか?」の質問には、「家族の大切さ」を感じさせる雰囲気がありますから、第2段落あたりで「食べ物の話題」を持ち出せば、スムーズに「家族との食事」に話題を転換することができるでしょう。ゆえに、「意図的にストライクを外した球」=「敬遠」と呼べるわけです。
最後は「暴投」です。これは多くの場合「遠すぎて失敗するリスク」があります。たとえば「友人との食事にお金をかけすぎていませんか?」「食品添加物に留意した食事をしていますか?」といった質問です。前者はお金の話題に、後者は食の安全性に、それぞれ話題が流れる危険性があります。そのまま「家族との食事の大切さ」に戻れない、あるいは戻れても強引な帰結になるリスクが高いため注意が必要です。
初級者は直球、中級者は外角攻め、上級者は敬遠に挑戦を。
何気なく「質問をするといいよ」という教員の助言は、予期しない形の質問となって学生の原稿に現れることがあります。その時、どんな狙いを定める質問が良いのかを教員が助言する必要があります。
初級学習者には、まず「ストライク直球ど真ん中」の質問で、スピーチの基本構成(質問とメインメッセージの明確な一致)を体得させることを優先します。一方で、中級以上の学習者には意図的に「外角いっぱい」や「敬遠」などの変化球を試させて、聴衆の思考を刺激する技術に挑戦させる指導が、学生の今後の成長につながります。
多くの場合、学生はそこまで考えずに、「何となくの雰囲気」や「会場の盛り上がり」を優先して質問を投げかける傾向があります。そんな時、それが「意図するスピード感が出ているか」や「狙い通りの場所に質問を投げられているか」を、教員がチェックすることは重要な指導の一環です。
野球のピッチャーが絶妙のコントロールを売りにするように、スピーチで質問を投げる時には、その狙いどころが極めて肝心です。教員としては、常に客観的な視点で、その狙いを審判する必要があるのです。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など