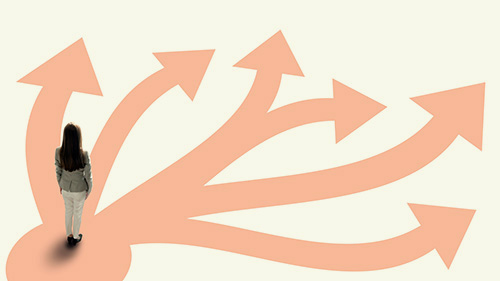【 サンドイッチ構造 】プレゼンターが知るべき基本の3層構造に慣れよう
「導入→本論→結び」の構造からプレゼンらしさが生まれる

クリームサンドは上下のビスケットがあってこそ美味しいように、スピーチやプレゼンにもこのサンドイッチ構造が必要です。最も伝えたい「本論」(中身のクリーム)を、「導入」と「結び」で挟み込むのが基本的な形。初めてのスピーチでは、この構造を守って「スピーチらしさ」を演出しましょう。
ご挨拶と予告をする「導入」- intorduction
いきなりサビから入るカラオケが歌いにくいのと同じで、スピーチにも適切な「導入」(introduction)が必要です。イントロの主な役割は、「今日は何の話をするのか」ということを予告(preview)して、話者と聴衆の意識が同じ視点に向かうように準備することです。
冒頭部分は、聴衆の注目が話者に最も集まる瞬間ですから、まずは穏やかな表情で話し始めるのが大切です。これは1対1で挨拶をするのと同じことですね。
イントロでは、本論に関係する質問を投げかけたり、「実は…」と聴衆を驚かせたりと、聴衆の興味をひくためのいつくかのパターンがあります。ただ慣れるまでは、そのようなテクニックを真似るよりも、感じの良い挨拶程度のトークのあとで "Today, I'm going to talk about ..." (今日は…についてお話します)のような言葉で「スピーチの方向性を定めること」を意識してください。
伝えたい内容を言い切る「本論」- body
イントロで方向性を予告していますから、本論はそれに続いて伝えるべきことを順番に話します。聴衆はあなたが準備した原稿を持ってはいませんから、話題は順序だてて分かりやすく並べることを心がけます。話す予定の項目を2つか3つに整理して、First ...、Second ...、Third ... と番号を付けながら話すと、「いま何の話をしているのか」が明確になります。
本論で注意すべきことは、話を中途半端にしないことです。スピーチの上達とともに、本論は「論証のプロセス」と呼ばれる役割を担いますが、慣れないうちは何よりも確実にストーリーを伝えきることが大切です。本論での話題が中途半端になると、「それがどうしたんだろう?」という疑問が残ります。きちんと話題にピリオドを打つ、ということを覚えておきましょう。
今日の話題を振り返る「結び」- conclusion
ひと通りの話が終わったら、締めに入ります。最後の「結び」の役割は、振り返り(review)です。本論で話した内容を簡潔に振り返ることで、大切なポイントを聴衆の記憶に留めます。"Today, I talked about A, B, and C." のようなシンプル表現でも良いので、キーワードだけでも繰り返しておくと効果的です。それが、スピーチやプレゼンの「終わりの合図」になります。
スピーチとプレゼンテーションにおける3層構造を簡単に整理すると次のようになります。
スピーチ/プレゼン 基本の3層構造
- 導入: 話の予告 - I am going to talk about ...
- 本論: 伝えるべき内容 - I am talking about ...
- 結び: 簡潔な振り返り - I talked about ...
それぞれの時制の変化を見れば、3層構造の役割が分かりやすいでしょう。導入が欠けると「いきなりか!」という唐突感がありますし、結びが抜けると「え?もう終わり?」になります。どのような長さの発表でも、この3層構造は変わりません。ぜひ意識してください。
こうして並べてみると、「導入」と「結び」は結果的に似たような話題になることが理解できるはずです。クリームサンドイッチの上下のビスケットが似ているように、スピーチにおいても「上のビスケット」(導入)と「下のビスケット」(結び)は、とても似ているのが特徴です。あとは、ぜひ美味しいクリーム(本論)を挟んでください!
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など