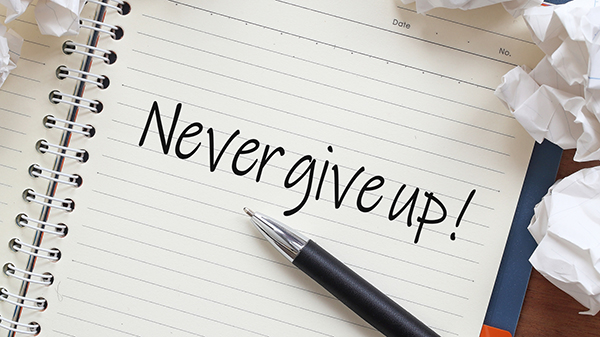初めてのスピーチコンテストに挑戦!今やるべき「たった3つ」のこと
初めてのコンテスト出場を「成功体験」に変える3つのヒント

初めて「英語弁論大会に出場する」と決めるのは、それだけで本当にスゴいことです!! 誰もがやらない挑戦をするというだけで立派。自分をしっかり褒めてあげましょう。今からやるべきことはたくさんありますが、出場を決めたタイミングで覚えておいてほしい「3つのやるべきこと」をお話します。どれも基本的なことですが、スピーカーとして意識すべき重要なポイントに絞りました。すぐに始めてみましょう。
1) 過去の受賞作品に触れて「スピーチの感覚」を掴む
どのようなコンテストでも、過去の受賞作には何らかの意味があります。賛否や好みが分かれる作品であっても、そこから必ず何らかの学びが得られるものです。コンテストを目指す者としては、まずはひとつのゴールともいえる過去の入賞作品を鑑賞し、「スピーチの感覚」に触れることを強くお勧めします。
過去の受賞作は、今からその世界に挑戦する人にとって、ひとつの目指すべき姿です。テーマや原稿の構成はもちろんですが、語りの様子や表情、ストーリー全体の盛り上げ方など、参考にすべきことはたくさんあります。スピーチの「到達地点」という意味で、「なぜこの作品が評価されたのか」を自分なりに分析してみることが大切。可能であれば、先生の意見も聞いてみると良いでしょう。
大会によっては、過去の受賞作品が公開されています。YouTube動画や、主催者のサイトなど、まずは大会名でGoogle検索をかけ、受賞作品の動画や原稿を探してみてください。自分が目指す大会の受賞作品が見当たらない場合には、類似する大会の受賞作をいくつか観てみることで代用できます。
全国規模のコンテストでは、本選出場者の原稿を収録した「大会パンフレット」が準備されます。過去の大会の印刷物(現物)を入手することは困難でも、電子版(PDF)であれば提供してもらえる可能性があります。自分が出場しようと考えている大会の主催者に確認をすれば、提供の可否を教えてもらえるはずです。
学内開催のスピーチコンテストの場合は、行事担当の先生や実行委員会に確認すれば、過去の受賞作品についての情報を教えてもらえるでしょう。映像の記録があれば助かりますが、映像は無くても原稿が残っていれば、それを確認しながら話の展開を参考にしてみましょう。
2) 身の回りから「社会を観察する習慣」をつける
弁論大会に出るということは「社会に物申す」ということです。社会に噛みついて、自分ならではの視点で問題を指摘し、解決策を論じる。これがスピーチの基本的な姿です。ひとりの存在は小さなものですが、コンテストの舞台を通じて、多くの人に自分のメッセージを伝えるのは、社会問題解決のための重要な一歩になります。
その舞台に備えて、まずは今日から、身の回りの出来事に幅広く関心を持ち「社会を観察する習慣」をつけてください。特に、今からスピーチのテーマを考えるという人にとっては、社会との接点を意識することは必須です。今まで以上に、社会の動きに敏感になっておきましょう。
身の回りの出来事は、意識をしないと何も問題を感じられません。逆に、目に見える一つひとつのモノや現象について真剣に考えると、そこからスピーチのヒントが見つかるものです。過去記事「スピーチテーマは「いつでも常に考える」ことで独自の題材に出会える」を参考に、社会に意識を向けるトレーニングを始めてください。
既にテーマが決まっている人にとっても、社会を観察し続けることは大切です。なぜなら、自分が話そうとするテーマは、社会の「ごく一部」を切り取っているだけに過ぎないからです。自分がスピーチでとり上げない領域の方がはるかに広大で、しかもそこに多くの聴衆の暮らしがあります。自分が話す話題以外にも、社会に誠実な関心を寄せることを欠かさないようにしましょう。
3) 声と語りを鍛え上げて「存在感」を高める
スピーチコンテストで入賞するスピーカーは、例外なく「語りの存在感」があります。大きな言葉でいえば「世界観」とも表現できる魅力です。(1)で紹介した「過去の受賞作」を観ても感じられると思いますが、この堂々かつ悠々とした存在感を手に入れるために、まずは今から「声」と「語り」を磨きましょう。
まず「声」は、何よりものインパクトを与えます。デカい声で驚かせようと言っているのではありません。大きな声を出せる「余裕」を持つことが大切なのです。この余裕が存在感を高めます。スピーチの中で、ここぞという場所で聴衆をハッとさせる程の豊かな声を出せるように、声量を高めることを意識した練習を始めてください。
そして「語り」とは、簡単にいえば「感情を声に乗せる技術」です。過去記事「【 100本ノック 】語りの素振り練習が実戦で差をつける」で練習法を説明しましたが、単に読む・話す、というのではなく「語る」のです。この違いを感じられるまで、自分の感情を声に乗せる練習をしてください。
「声」も「語り」も、その練習プロセスの中で克服しなければならないのが「恥ずかしさ」です。大きな声も、感情がこもった語りも、実は「恥ずかしさ」が強烈に邪魔をします。スピーカーは人前に出て、堂々と社会に噛みつく存在です。そんな存在が恥ずかしがっていては、聴衆はついてきません。コンテストに出ると決めた勇気と自信をもって恥ずかしさを乗り越えましょう。
これら「3つのこと」を最初に意識して取り組めば、初めてのスピーチコンテスト出場という挑戦を通じて、自分でも驚くほどの上達が感じられるはずです。みなさんとコンテスト本番の舞台でお会いできるのを楽しみにしています!
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など