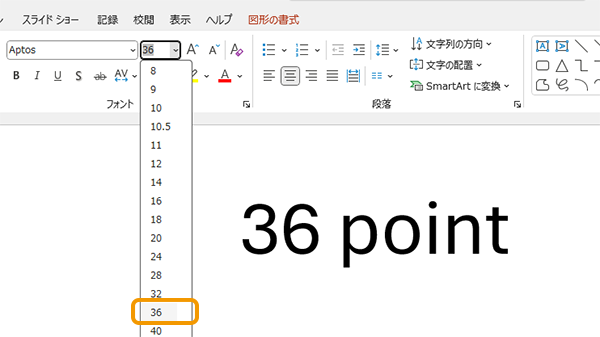プレゼン会場は明るく!映画館化を防ぎ話者の存在感を高める照明術
プレゼンの没入感は話者とスクリーンの共演から

プレゼンを発表する際、必要以上に会場を暗くしていませんか? 映画とプレゼンでは、照明の考え方がまったく違います。プレゼンの主役は、スクリーンに映し出されるスライドだけではありません。話者自身、つまりスピーカーとスライドの「共演」こそが、聴衆の心を引き込む鍵になります。そのためには、会場の照明は極力明るく保つことが重要です。
スライドが判読できる限り部屋は明るくする
かつて、プレゼンの際は映画館並みに照明を消すのは当たり前でした。なぜならプロジェクタの明るさ性能(ルーメン)が低かったからです。暗いプロジェクタで映写されたスライドを見るためには、部屋を暗くするほかに方法が無かったのです。
現在のプレゼン環境は違います。プロジェクタも明るくなり、スクリーンも大きくなって、プレゼンを発表するためのコンディションは格段に良くなりました。にもかかわらず「カーテンを閉めて電気を消す」のが恒例行事になっているのはもったいないことです。
映画の場合、会場を暗くして全注目をスクリーンに集めるのが基本です。これは「映像世界への没入感」を高めるため工夫です。しかしプレゼンでは、スクリーンとともに「話者の存在感」も際立たせる必要があります。そのためには、スライドが判読できる限りにおいて、部屋を極力明るくしなければなりません。
講演会場が会議室や教室などの場合、会場前方を照らすための「黒板灯」があります。多くの場合、この前方照明を消すだけで十分です。直射日光がスクリーンに当たる場合を除いて、カーテンを閉める必要もありません。会場は映画館ではありませんから、スライドさえ見えれば、あとは明るい方が話者の表情がしっかり伝わります。さらに話者自身も、聴衆の顔が見やすくなって一石二鳥です。
プレゼンの没入感はスクリーンと話者の一体感にあり
過去記事「プレゼンでは演台を離れてスクリーンの横に立つだけで存在感が高まる」で紹介した通り、スピーカーが立つ基本位置はスクリーンの横です。プレゼンにおける「没入感」は、スクリーンとスピーカーが一体となって語り掛ける姿に、聴衆が引き込まれるときに生まれます。
プレゼン準備のために会場に入ると、既に電気が消され、カーテンも閉じられている場合があります。これは主催者の配慮によるものですが、そんな時でも遠慮せずに「電気をつけてみてもよろしいでしょうか」「カーテンを触ってもよろしいですか」と尋ねてください。
テスト用に、文字と写真が混在するスライドをスクリーンに映した状態で、ひとつ一つ照明をつけたり、カーテンを開けたりして、スクリーンの映り具合を確認します。直接的な光がスクリーンに入り込むような場合を除いては、照明をつけても、カーテンを開けても、思うほど影響がないことに気づくでしょう。
とはいえ、新商品や新サービスに関する画像を最高品質で映写したい場合もあるはず。そんな場面では、その時だけ部屋の照明を消せばよいのです。そうすれば「照明が消える」ということ自体が、まさに映画館のように、次に続く「映像世界への没入感」を高める合図として作用するでしょう。
当然のことながら、プレゼンの主役はスライドではありません。スライドと同じか、それ以上に重要な存在がスピーカーです。次回のプレゼン会場では、スピーカーの顔が見えないような明るさだけは避けるように工夫をしてみてください。想像以上に、話者の存在感が強化されるはずです。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など