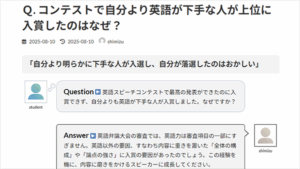学生の上達速度と到達レベルを予測し、スケジュールと目標を設定する。
何の上達に重きを置くか、学生の吸収力と到達度のバランスを取る。
※これは教員向け(教え方)の記事です。

「この学生の上達は、コンテストに間に合うだろうか…?」英語スピーチやプレゼンの指導をしていると、そんな不安を感じることがあります。学生の現在の実力と、コンテスト当日の目標レベルの差をどう埋めるか。これは教員の腕の見せ所です。到達レベルをゴールとし、学生の「現時点の実力」と「上達速度」を計算しつつ、指導内容を切り替える必要があります。その要点を解説します。
「テーマ、執筆、メモライ、デリバリー」の4段階で調整
スピーチでもプレゼンでも、コンテストに向けた準備段階は、ざっくり分けて以下の4段階になります。各段階にどの程度の時間を割くかは、指導学生の能力や学習力によって調整が必要です。その大まかな目安として、コンテスト応募までの練習期間を割り当てる例(%)を併記しました。
- テーマ検討 [40%]
発表に適したテーマを検討し、決定する段階。 - 原稿執筆 [20%]
確定したテーマに基づいてスピーチ原稿を執筆する段階。 - メモライ(原稿暗記) [10%]
原稿の内容を正確に暗記し、口頭で再現する段階。 - デリバリー [30%]
メモライ済のメッセージを、効果的に伝達する段階。
全国オープンの弁論大会やプレゼンコンテストへの応募を検討する場合には、上記の一連のプロセスを完了するには少なくとも3か月、通常は半年ほどを必要とします。仮にその期間が2か月と短く、あるいは10か月と長くなった場合、上記の(1)~(4)のどこにどの程度の期間を割いて指導するかが成否を決めます。
私の研究室では、最も時間をかけて取り組むのが「(1)テーマ検討」です。テーマは、最終的なスピーチの質を大きく左右します。どれだけデリバリーが上手でも、そもそものテーマが貧弱であれば、コンテストで入賞することはないからです。
また、テーマの検討期間は、スピーチに向けた心構えや覚悟を養う期間でもあります。テーマの検討に最も長い期間を充てるのは、ひとりの学生を一人前のスピーカーに育てるための意識づけの意味を持っています。さらに、この期間には学生の英語力を確かめたり、デリバリーの資質をチェックすることも可能です。
現時点の能力、上達速度、練習期間のバランスが重要
上記(1)~(4)の、それぞれに配分する練習期間の「%表記」は、学生によって変わります。その際、考慮すべきは、「(A)現時点の能力」「(B)上達速度」「(C)指導期間」の3点です。
「(A)現時点の能力」とは、指導開始時点において、上記(1)~(4)がどの程度のレベルにあるかを示します。既にテーマが絞られていれば、「(1)テーマ検討」の期間は圧縮できますし、逆に英語を暗記することが苦手であれば「(3)メモライ」には少し長めの期間を設定する必要があります。
「(B)上達速度」とは、指導学生がどの程度の学習力や吸収力をもってスピーチ練習に取り組めるかを先生が判断するものです。飲み込みが早く、何でも要領よく身につけられる学生なら、「(4)デリバリー」の期間を短くして、その分「(2)原稿執筆」を長く設けるということもあるでしょう。
「(C)指導期間」はスケジュール設定の要です。全体的な練習期間がどれだけあるかによって、各練習項目の配分は大きく変わります。たとえば「(2)原稿執筆」や「(3)メモライ」は、練習期間の長短にあまり影響を受けず、ある程度一定です。逆に、練習期間が長くなるほど、「(1)テーマ検討」と「(4)デリバリー」に割ける時間は長くなります。
学生のラーニングカーブを勘案して指導計画を決める
上記(A)(B)(C)に加えて、もうひとつ考慮すべき要素があります。それは「学習曲線」と呼ばれるラーニングカーブ(Learning Curve)の存在です。ラーニングカーブとは、スピーチの上達が直線的に伸びるのではなく、各学生に応じて曲線的な伸びを示す現象のことです。
特にデリバリーの練習においては、このラーニングカーブの個人差がとても大きいです。なめらかに右上がりに推移する線グラフをイメージしてみてください。デリバリーの練習では、最初は練習するほどに滑らかに上達しますが、あるレベルに達すると、少し練習しただけでは大きな変化が見られなくなります。これがいわゆる「高原期」(プラトー/停滞期)という現象です。
練習期間が長い場合は、この「高原期」を一種のスランプのように感じる学生もいます。予選応募の締め切り日までに、最終目標とするレベルへの到達を狙うには、指導学生に起こりうるラーニングカーブの推移を事前に予測して、余裕のある練習計画を立てる必要があります。
練習期間が足りない場合にどこで妥協するか
スピーチの指導経験を積むほどに、「この時点でここまで出来ていれば、あと何週間あれば目標レベルに達するか」ということが予測できるようになります。逆に言えば、思いのほか上達が進まない場合、指導期間が限られている以上、何かを「妥協」せざるを得ないということです。その際、どこで妥協するかが重要です。
よくある失敗は、何かと原稿準備とメモライに時間を取られ、デリバリー練習がおろそかになるケースです。スピーチの最終製品としての印象を決めるのは「デリバリー」です。優れた原稿でも、デリバリーが貧弱であれば内容を伝えきることはできません。
もし、デリバリーで妥協をする場合には、「ジェスチャー」(gestures)の指導は後回しでも構いません。ジェスチャーは絶対に必須というものではないからです。
かつて私の研究室に所属していた学生がスピーチコンテストに挑戦する際、デリバリーに十分な指導期間を割けなかったことがあります。その際は、思い切ってジェスチャーを最重要の1か所に限定し、それ以外の時間は、語りやアイコンタクトの指導に集中しました。それが奏功し、全国大会決勝では準優勝を収めています。
プレゼンテーションの場合であれば、思い切ってスライドを減らし、全体の情報量を圧縮することで、全体の練習時間を確保することも選択肢のひとつです。スピーチなら、全体の単語数を減らすということです。仮にどこかで妥協する場所があっても、それ以外の部分で輝く場所を作れば、立派なプレゼンは成立します。
経験不足ゆえ、学生は自分で練習計画(スケジュール)を考えることはできません。ぜひ上記の基準を参考にして、各学生に適した練習計画を立てて、指導にあたってください。ポイントは「とにかく早めに進めるよう指導すること」に尽きます。学生の成長と、大会でのご成功を祈ります。
■ 関連記事
▶ 英語スピーチやプレゼンの指導は「ひと言で言えるか」を尋ねて確認 [リンク]
▶ Q. 英語スピーチのジェスチャーがぎこちない [リンク]

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など