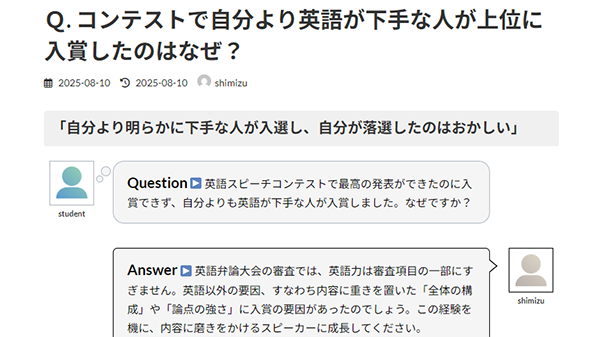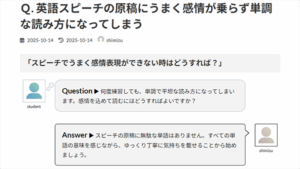無念の予選落ち。大会審査を通過できない時こそスピーチを続ける意思を持って!
どんな時にも「挑戦の原点を忘れない人」はいつか勝利する

スピーチコンテストやプレゼン大会では予選落ちがつきものです。がんばって予選に応募をしても、本選に進めるのは10名程度。冷静に考えれば、応募者のほとんどが落選します。それでも応募にかけた熱意が大きいほど、残念な気持ちも強くなるのは当然でしょう。ここでは、落選から次の一歩を踏み出すための心構えや、今後の向き合い方を考えます。
結果を潔く受け入れ、気持ちを切り替えて次を目指す。
大きな大会になれば、50人から100人レベルの応募者がいます。その中で本選に進める人はごくわずかです。自分がスピーチに投入できるリソース(時間・労力・熱意)をすべて投入しても、予選通過が叶わなかった場合には、落ち込むよりも次のチャンスを目指して気持ちを切り替えた方が良いです。これが原則的なアドバイスです。
決して「やみくもに応募すればいい」という訳ではありませんが、積極的に応募を続けることでチャンスを獲得する機会を増やすということには合理性があります。ひとつの大会がダメだったからといって、他もダメということはまったくありません。潔く次のチャンスを狙うべく、応募を続けてください。
その年の大会ごと、応募者の状況によって結果は変わる。
ある大会の予選会では高評価を得たスピーチが、他の大会では選外になった、ということは普通に起こります。スピーチの良し悪しは絶対評価ですが、他者と比較されるコンテストでは相対評価になります。どれだけ自分のスピーチが素晴らしくても、それ以上に素晴らしいスピーチが登場すれば、最終的な順位は下がります。これはコンテストの宿命です。
逆に、自分ではあまり自信がないスピーチでも、それを高く評価する審査員に恵まれれば、予選を通過する可能性は十分にあります。そういう意味では、実力も大切ですが、その大会やその年の状況によって、常に結果が変化するという現実を知っておくことも大切です。それを私は「縁(えん)」と呼んでいます。
落選の通知を受けた時は、確かにその大会には「縁」が無かったかもしれません。でも他の大会となればまた別の話。本人にやる気があり、継続的に自分のリソースを投入する意思がある限り、挑戦は続けるべきだと考えます。
落選の経験で得た学びは、必ず成功への節目になる。
ここから先は「もっとやってやろう」という意欲のある人に向けて書きます。
今後のさらなる飛躍をめざすなら、落選通知は、自分自身を奮起させるきっかけを与えてくれます。予選結果の審査用紙が返却される場合、見るべき場所は審査員のコメントです。ここに自分に心当たりがあることが書かれている場合、それは改善した方が良いです。
必ずしも予選審査員の言いなりになる必要はありません。ただ、この機会にある程度改善しておかないと、また次も同じ問題で審査が不利になる可能性があります。
個別の審査項目の配点は、それぞれ一喜一憂するほどのことはありませんが、極端に低い点が付いている項目があれば、それは改善したほうが良いです。逆に、極端に高い点が付いている項目があれば、それは自分の強みとして自信を持ってください。
本気で目指すなら、人よりも多くの練習時間を投じる。
コンテストは多くの人が、限られた本選出場の椅子を狙って切磋琢磨するイベントです。たとえあなたが精一杯努力をしていると思っても、それ以上に努力をしている人がいるのが常です。短期間で劇的に原稿や英語力が改善されることはありません。とすれば、最終的にどれだけの練習時間を投入できるかが勝敗を分けます。
「予選のためにそこまでしなくても」と思う人もいるでしょう。それも間違いではありません。でも予選を通過しなければ、本選出場は叶いません。予選は、すでに本選の一部です。その意識で、とにかく練習時間を増やし、原稿の改訂や予選用の音読練習に費やしてください。
悔しさを忘れず、新たな目標を叶える底力にできるか。
やると決めたら、あとは実力を磨きながら、継続的に多くの大会に応募し、自分に訪れる「縁」を待つことです。友人やライバルに先を越されても、焦らずに着実に練習を続けるのです。自分が最初にスピーチコンテストに挑戦しようと思った時の「初心」を忘れることなく、自分が持てるリソースを惜しみなく投入できる人が、最終的には勝利を収めます。
最後に、かつて私の研究室に所属していた学生のお話を紹介します。あるゼミ生は、学内で開催される弁論大会に応募しました。同じ研究室の仲間が第一次予選、第二次予選を通過し、本選へと順調に駒を進める中、その学生は第一次予選で敗退。相当に無念な予選落ちだったはずです。しかし彼女はそこで諦めず、その反省と悔しさを胸に学外の全国オープン大会に挑戦して予選を通過。決勝の舞台では見事、優勝を収めました。
人に負けない「挑戦の意欲」を失わない限り、予選落ちは単なる通過点にすぎません。誰にも必ずチャンスは訪れます。その時に万全の準備が整っているかどうかが運命を決めます。心を強く持ち、日々研鑽を続けてください。
いつかどこかの本選大会で、皆さんのスピーチを審査できるご縁を楽しみにしています。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など