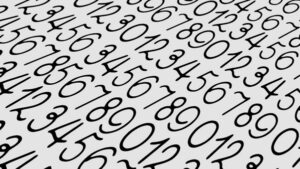話題の並列は陳列どまり。論証材料は直列式でこそ勝てるスピーチになる!
論証材料を並べるだけではダメ。融合作用のある話題を選んで!

説得型スピーチに必要な論証材料を、とりあえず原稿の中に並べるだけで満足していませんか? 勝てる説得型スピーチを目指すなら、論証材料の「並べ方」と「相互のつながり」が鍵を握ります。単に話題を並べるだけでは不十分。それでは乾電池の並列つなぎのように、論証力が電池1個分のパワーに留まってしまいます。あなたの論証術を「直列つなぎ」に変える方法を紹介します。
並べるだけの並列式では「1+1=1」の論証力に留まる
資格試験のスピーキングテストにおける論述の基本に、「3つの理由を挙げる」というスタイルがあります。これは、最初に結論を述べて、次に理由を2つか3つ紹介し、最後にもう一度結論を述べる、というものです。論証型スピーチの雛型として広く知られているので、これで練習をしたことがある人も多いでしょう。
資格試験の対策や、説得型スピーチの最初の一歩として、この形をマスターすることは大いに意味があります。しかしこの論証方法は、主張を支える根拠(論証材料)を、単に並列状態で「スピーチ内に陳列している」だけの状態。その論証力には限界があります。
ここで「乾電池の回路」を思い出してください。「並列つなぎ」でいくつ電池(論証材料)をつないでも、その力は乾電池1個分です。説得型スピーチでコンテストに勝つためには、論証材料を集めて並べただけという並列状態から、真のパワーを発揮できる「直列状態」に変換する必要があります。
話題を連携させる直列式で初めて「1+1=2」になる
並列式と直列式の決定的な違いは、その接続にあります。乾電池の直列つなぎを思い出してください。ひとつ目の電池を通ったあと、次の電池につながります。そうすることで「1個+1個=2個」のパワーを発揮します。
実は、スピーチの論証材料についても、これと同じことがいえます。並列式が単なる「陳列」だとすれば、直接式は「連携」です。並列式か直列式かを分けるのは、「一つひとつの論証材料が次の論証材料に結びついているか」です。
ではここで、「地震の備えをしよう」という説得型スピーチの「3つの論証材料」を検討してみましょう。並列式・直列式の論証材料の典型例を紹介しますので、その違いを感じ取ってみてください。
「並列式」の論証材料
- 友人が過去に地震で被害を受けた。
- 南海トラフ地震に備える必要がある。
- 避難用品を備蓄する家庭が少ない現状にある。
「直列式」の論証材料
- 友人が過去に地震で被害を受けた。
- そこでは、地震の際に避難用品の圧倒的な品不足があった。
- それでも、避難用品を備蓄する家庭が少ない現状にある。
並列式の3つの話題(論証材料)は、それぞれ単体として「地震の備え」の訴えに合致しています。スピーチの中で、First, Second, Third, という具合に紹介していけば、それなりの説得力はあるでしょう。
一方、直列式の論証材料も同様に、それぞれが「地震の備え」の必要性を訴えるものです。しかし直列式の材料は、それぞれがきちんと相互に接続し、全体としてひとつの「ストーリー」を作り上げています。これによって、はじめて3つの論証材料が持つ力が合算されるのです。
さらによく見てください。並列式と直列式の違いは「2番」のみです。つまり「並列式」でスピーチを書いている人でも、少し工夫をすれば、十分に「直列式」に転換することが可能ということです。そういう視点で上のふたつの例を見比べてみれば、並列式を「単に陳列しただけ」と表現した理由が理解してもらえるはずです。
この「少しの工夫」とは、「地震の備えの重要性」という社会問題を、さらに深く、誠実に、考え続けることです。そうすれば、それぞれの論証材料をつなぐことのできる「新たな論証材料」に出会うことができます。
論証材料は、それぞれが連携してこそ意味がある!
説得型の英語スピーチは、ひとつひとつのパーツが互いに意味を持ち、連携しあうように設計するのが基本です。「論証の基本」を身につけたあとは、論証方法の奥深さについても、ぜひ研究してみてください。
スピーチの論証方法については、この他にも「1+1」が3以上になるような説得術も存在します。論証ひとつをとっても、説得型スピーチの奥深い面白さがあります。聴衆のことを考えながら、どのようなストーリーを構築するのが良いかと思いを巡らせることは、話者の人間性を高める大切な取り組みになります。

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など