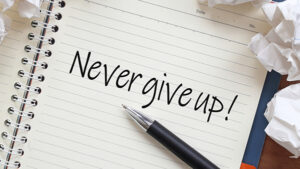「スピーチでは質問をすると効果的」のウソ。万能ではない"質問"の怖さとは
大切なメッセージは、質問より「断言」でこそ伝わる。

英語スピーチやプレゼンの教本を開くと、必ずと言っていいほど「聴衆に質問を投げかけましょう!」というアドバイスが目に留まります。聴衆との対話を生み、注目を集めるための効果的なテクニックとして、誰もが一度は試したことがあるでしょう。でも実は、安易な質問には「聴衆を置き去りにしてしまう」という意外な怖さも。安易に質問に頼らず、よりスピーチらしい強さを伝える「断言」の力を紹介します。
頻繁な質問は、聴衆が答えを考える負担を生む。
特に中学生や高校生の英語スピーチでよく見られるのが「質問で始める」プレゼンです。おそらく先生の助言に従って、そうなっているのでしょう。もちろん「単体」であれば何の問題もありません。しかしそれが何度か、あるいはいくつかの場所で登場すると、聴衆にとっては都度、答えを考える負担になります。
たとえば「食育」に関するスピーチを考えましょう。冒頭で"Did you have breakfast this morning?" [今朝は朝食を食べましたか?]という程度の質問であれば、聴衆には何の負担もかけません。でもそれに続いて"How many times do you skip breakfast within a week?" [週に何回朝食を抜きますか?]や"How many items did you have on the table?" [テーブルには何品ありましたか?]といった質問が続くと、聴衆は少なからず圧迫感を感じます。審査員であればなおさらです。
確かに、聴衆との一定のコミュニケーションが成立しているように見えますが、客観的に見れば、話者が聴衆の思考力を強引に奪っている現状があります。過去記事「聴衆に反応を強制しても本当の対話にはならない」(教員向けの記事) にも通じる考え方ですが、聴衆に負担をかけるアプローチはお勧めできません。
時に、冒頭から強烈な質問が飛んでくることがあります。たとえば、"What is the most important thing in your life?" [あなたの人生でもっとも大切なものは何ですか?]です。恐らく、話者はこの質問を通じて「何かを真剣に考える瞬間」を聴衆と共有する意図があるのでしょうが、いきなりこんな超重量級の質問を冒頭で投げつけられたら、聴衆はもう完全にお手上げです。
「質問をする」というテクニックはまったくもって「万能」ではありません。少しでも、くどかったり、重かったりすれば、聴衆との対話どころか、聴衆を簡単に置き去りする「怖いもの」だという事実を知っておいてください。
質問の意図を汲んで「断言」した方が強い!
質問が怖いとなれば、どうするか。そのひとつの答えが「断言」です。そもそもスピーチとは、話者の考えを聴衆に訴えるもの。質問をするくらいなら、その背後の意図を反映させて「断言」すれば良いのです。
先の「食育」のスピーチの例を振り返って、比較をしてみましょう。そもそも"Did you have breakfast this morning?"という質問をする意図を考えてみます。(1) 朝食の大切さを意識させたい、(2) 朝食についてのスピーチをすることをほのめかしたい、(3) 聴衆の注目を集中させたい、(4) 聴衆の朝食に興味があることを伝えたい、というあたりでしょうか。
であれば、"Breakfast is important." [朝食は大切だ]と言い切る方が良いです。理由は簡単。「短く断言できているから」です。これはスピーチやプレゼンにおける基本です。加えて、「朝食は大切だと伝えるのが、そもそもの質問の意図だから」です。
同様に、"How many times do you skip breakfast within a week?"と言う代わりに、"Many young students often skip breakfast." [多くの若い生徒たちは、よく朝食を抜きます]と断言する。"How many items did you have on the table?"の代わりに、"Some students even have only a single chocolate donut on the table." [中には、たった一つのチョコドーナツだけがテーブルにある学生もいる]と言い切る。
つまり、質問をするというアプローチによって、時に「主張を遠回りさせることがある」という現実に気づいてほしいのです。質問は、頻度と内容に注意し、その質問が効果的であると思われる時に使いましょう。
蛇足ですが、多くの人がスピーチで「質問」のテクニックを使うのであれば、なおのこと「自分は使わない」という選択には意味があります。人と同じ戦略をとらないこと。人とは違う工夫をすること。これは、スピーカーに必須の「スピーチマインド」です。覚えておいてください。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など