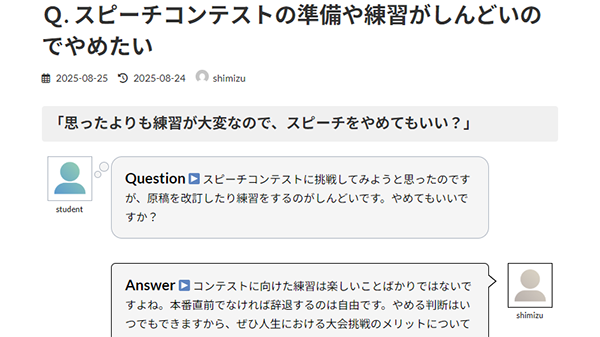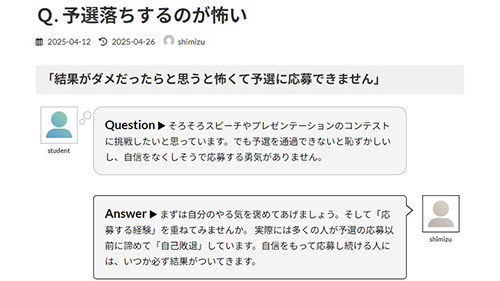挑戦をあきらめない意志を持つ!スピーカーのための「2つの目標設定術」
最初の一歩からの上達を記録し、常に目標を定めなおす。
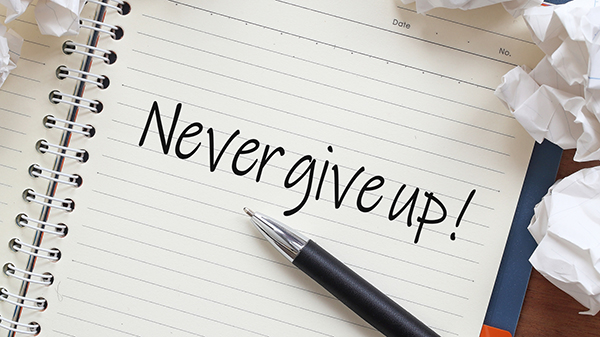
スピーチやプレゼンは練習とともに確実に上達します。しかし、上達の程度は常に上昇を続けるわけではありません。自分の上達に自信が持てなくなった時、引き続きスピーチと向き合うためには強い意志が必要です。そんな時には、スピーチを始めようと思った瞬間の気持ちを思い出しましょう。そのうえで「対外的」と「対内的」のふたつの目標を意識し、少しずつでも前進を続けることが大切です。
客観的評価を勝ち取る「対外的な目標」
まずひとつ目は「対外的な目標」です。分かりやすくいえば「コンテストで勝ちたい!」といった目標がこれにあたります。自分の努力を、外部の客観的指標で評価されるのは、なかなか勇気のいることです。その分だけ、目指した評価を得られれば、強い自信を獲得することができます。
コンテストのように受賞者が限定される場面では、対外的な目標の達成はとても厳しくなります。スピーチの初心者であれば、まずは「音声審査に応募する」「予選を通過する」といった直近の目標を設定し、それに向けて日々の努力を重ねるのが現実的です。
「応募するのが目標なんて簡単だ」と言う人がいるかもしれませんが、全国に無数のスピーカーがいる中で、実際に応募まで至る人は相対的にごくわずかです。つまり「誰でもできる」と思われている目標でさえ、そこに到達するまでに挫折する人が本当に多いのです。
対外的な目標を設定する場合には、自分にとって「ちょっと高いかな」という程度のレベルで設定し、ひとつずつ成功体験を積みながら、自信を獲得していくことをお勧めします。最初からいきなり全国大会で入賞できるのは極めて稀なこと。少しずつ自信を強化できるような目標設定を心がけましょう。
自分の成長を基準に設定する「対内的な目標」
対外的な目標は外部の目が入るだけに基準は厳しくなりがちです。予選落ちが続いたり、審査のフィードバックに厳しいコメントを書かれたりして、自信を失うこともあるでしょう。そこで覚えておいてほしいのが、自分の中に目安を置く「対内的な目標」を一緒に持っておくということです。
たとえば、「特定の発音を克服する」「スピードを維持できるようにする」「張りのある声を身につける」など、今は出来ていないけれど、近々達成したい「自分自身の目標」がこれにあたります。いわば「内省的視点を持つ」とも言えるでしょう。
スピーチコンテストやプレゼン大会に挑戦するとなると、どうしても「入賞」が眼前の目標となりがちです。でもそれは、多くの「対内的な目標」を乗り越えた、その先にあるゴールです。大きな目標を掲げる時でも、目の前の一つひとつの目標をおろそかにしないことは、ひいては「目の前の課題から達成感を得る秘訣」でもあります。
大きな全国規模の英語弁論大会を目指すとなると、準備から予選応募、本選出場まで、期間も規模も大きな準備が必要です。だからこそ、日々小さな達成感を得られる「対内的目標」を設定し、それを更新し続けることを忘れないでください。
地道に努力を続けたからこそ得られる経験がある
練習のプロセスにおいて、誰しもうまくいかないスランプの時期はありますし、上達が感じられなくなって練習が嫌になる時期は必ずあります。それでも真っ当に努力を重ねてきたスピーカーであれば、実際には着実に上達していることがほとんどです。どうか安心してください。
私の研究室に所属していたある学生は、3年生から全国オープンのコンテストに応募を続けていました。残念ながら予選を通過できない日々が続きましたが、その学生は「対内的な目標」を持ち続けて、自身の発音や原稿の構成力を磨き続けました。その結果、卒業を目前に控えたプレゼンコンテストで見事に全国優勝を収めました!
コンテストに挑戦する皆さんは、ぜひ「対外的」「対内的」のふたつの目標を意識して、日々の練習を通じて「挑戦をあきらめない強い心」を獲得してください。それもまた、スピーチに熱心に取り組む人だけが手にすることのできる、貴重な財産です。がんばりましょう!
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など