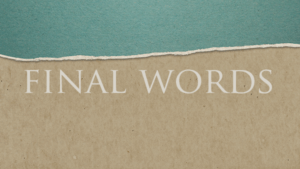原稿作成と音読練習は並行して取り組むからこそ「ライブ感」が磨かれる
原稿作成で迷ったときには音読し、録音し、客観的に感じてみる。
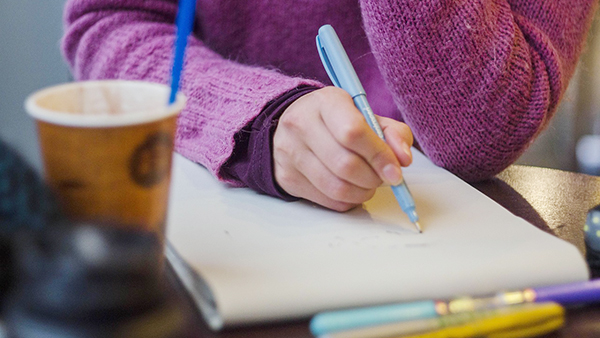
スピーチやプレゼンの原稿改訂を続けるほどに、自分の原稿が良いのか悪いのかも分からなくなる時があります。自分の原稿にどっぷり浸かってしまうと、自分の言いたいことが見えなくなる現象です。そんな時は、一度PCから離れてみましょう。そして、原稿を「声に出して」読んでみてください。できれば録音したものを確認し、自分の「スピーチの現在地」を確認してみる作業が大切です。
原稿は語りの設計図。声は語りのライブ感を伝える。
当然のことですが、聴衆は原稿を持っていません。大きなコンテストであれば大会冊子に原稿が掲載されることはあるかもしれませんが、それでも聴衆が原稿を目で追うことはありません。スピーチやプレゼンは、原稿なしに、目の前のライブショーを楽しむ芸術です。
その基本に立ち返れば、原稿とにらめっこばかりしていては、スピーチのライブ感を見失います。原稿で行き詰ったり、表現で迷った時にはなおのこと、声に出して語ってみてください。語ってみることで、思いのほか素直に表現できていたり、あるいは思ったより小難しく聞こえたり、現時点のスピーチの輪郭が感じ取れます。
原稿は、語りの設計図です。最終製品としての価値はその発表にあります。この点は、小説家とは大きく異なります。だからこそ、PCに向かってひたすら原稿を改訂するだけでは、プレゼンの本当の姿は見えてきません。節目節目でPCから離れ、聴衆を想定しつつ音読する習慣をつけましょう。それはまた、新鮮な気分転換にもなるはずです。
原稿作成にかける時間が長すぎるのも要注意
スピーチの最終製品がステージ上のライブショーであることを考えれば、スピーチの準備期間において、ひたすら原稿改訂に時間を費やすのは考えものです。極力早めに「語り」の練習に移行するか、あるいは原稿改訂と語りの訓練を同時並行で進めることをお勧めします。
過去記事「学生の上達速度と到達レベルを予測し、スケジュールと目標を設定する」(教員向けの記事です)では、原稿執筆に配当する準備期間を「全体の20%」とすることを提案しました。このバランスもまた、「原稿ばかりに向き合っているとスピーチの本質を見失うリスクがある」点を考慮しています。
スピーチを学ぶ学生に「語りの練習の進み具合」を尋ねると、よく「まだ原稿が出来ていないんです」という返答が帰ってきます。それに対する私の返答は「だからこそ、語りに取り組んでください」です。「空気の読めない教員」のようにも聞こえますが、原稿と語りはふたつでひとつです。原稿だけに集中するという性質のものではないことを忘れないでください。
英語スピーチとプレゼンテーションの共通点に、「音にして初めて感じられる気持ち」があります。熱意や興奮、そして喜怒哀楽も、声に出して初めて聴衆に伝わるもの。原稿はあくまでもスピーチの設計図です。だからこそ、実際に声を出して「音にする練習」を繰り返すことが、聴衆の心に届く「強いスピーチ」づくりへの第一歩になります。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など