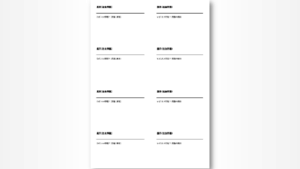丸投げで満足せず、聴衆の行動を促す「今すぐできる解決策」の訴え方
なぜ、解決策に「誰もが今すぐできる行動」が重要なのか?

スピーチで素晴らしい解決策を提示したつもりでも、聴衆が会場を出た瞬間に忘れ去られてしまう…。そんな経験はありませんか? 聴衆は、国や政府に丸投げするだけの解決策には共感しないものです。説得型スピーチでは、誰もが解決策の一部となり、すぐにでも行動に移せる提案をすることが大切だと考えましょう。
立派な解決策よりも、身近な解決策が重要。
スピーチコンテストの審査員をしていると、他者に解決を「丸投げ」しながらも、まるで自分自身がその問題の解決に貢献したかのように語るスピーカーに出会うことがあります。そんな時、ふと「優れた解決策とは何だろう」と考えさせられます。
解決の対象となる社会問題が大きくなるほど、個人がその問題の解決に寄与できる余地が少なくなるのは理解できます。それでも「政府は〇〇すべきだ」「国はもっと〇〇に目を向けて…」といった提案は、結局のところ他者への丸投げであることに気付く必要があります。
たとえば社会格差の拡大に伴う「貧困層の増加」の解決策を考えてみます。法的な対応や、補助金による手当、教育制度の拡充などは、当然ながら立派な解決策の一部です。しかし、それを訴えるだけでは、話者自身の責任を棚上げしたかのような「解決策提案コンテスト」のように響くでしょう。話者自身の関与を伴わない提案は、聴衆に「この話者は他人に責任を押し付けている」という印象を与えます。
大切なのは、話者自身を含む聴衆全体がひとつになって、何が出来るかを訴えること。先ほどの貧困層の増加を例に挙げれば、貧困層を支援するためのボランティア活動への参加や、学校での社会連携教育や探究活動を通じた支援の取り組みなどは、話者も聴衆も同じ目線で実践できる解決策になります。
立派な解決策を「上から目線」で提示するだけでは、聴衆の心に響きません。まずは自ら率先して何をするのか、そしてそれに聴衆をどう巻き込むかが、共感を呼ぶスピーチになるかどうかの分かれ目です。
解決策までを含んでスピーチのテーマを考える
説得型スピーチに取り組んでいる学生と話をしていると、「私のスピーチは、なかなか解決策を考えるのが難しいんです」という声を聞きます。もし話者が本当にそう思って苦しんでいるなら、そのテーマでスピーチをすることは諦めて、別のテーマを考える方がスムーズです。
そもそも、説得型スピーチを実践する際は、テーマを決めてから解決策を考えるのではなく、解決策が出せるテーマを選ぶ必要があります。つまり、テーマと解決策は表裏一体であり、テーマだけが先行することはありません。解決策が出せない社会問題を、安易にテーマに選んではいけないのです。
過去記事「説得型スピーチ構造用紙|連続入賞を達成する基本的枠組み」で紹介した説得型スピーチの構成部品は、どれかひとつが欠けても強いスピーチにはなりません。解決策はもとより、テーマに連動する論証材料(データや事実)があるか、明るい未来が提示できるか、といった要素も、テーマの決定前に一括して検討する必要があります。
会場を出る瞬間に覚えてくれている解決策を訴える
優れた解決策とは、話者自身や聴衆ひとり一人が実践できるものです。逆に言えば、そんな解決策を提示できる社会問題が優れたテーマだということです。聴衆にとっては、今すぐにでも取り組める解決策は、国や政府に丸投げする提案と比べて、自分自身の課題として認識され、長く記憶される可能性が高まります。
解決策を提示する際は、聴衆が会場を去る瞬間に思い出してくれるように「今日からすぐに取り組める行動」を意識して呼びかけてください。そうすれば、あなたのスピーチは単なる情報伝達で終わらず、聴衆の心に火をつけ、行動変容を促す力強いメッセージとなります。
テーマと解決策が明確につながり、聴衆との一体感を感じられる語りこそ、誠実さがあふれる説得型スピーチの真髄だと言えるでしょう。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など