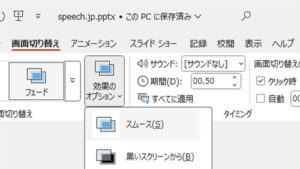イントロで迷ったら"I'm going to talk about ..."で方向性を示す
スピーチの導入部では「何を話すか」をハッキリさせるのが使命
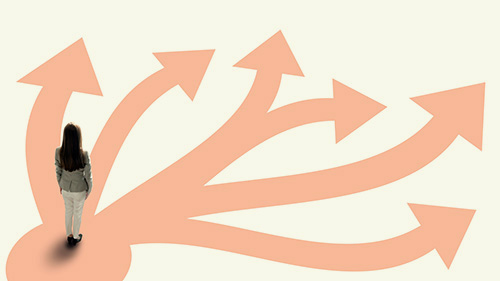
スピーチやプレゼンの導入(introduction)には、聴衆に話題の方向性を示すという大切な役割があります。面白いイントロにこだわり過ぎた結果、結局「何の話をするのか」が曖昧になったスピーチをよく見かけます。迷ったら、とりあえずイントロの終わりで"Today, I'm going to talk about ..."と言いましょう。
冒頭で何の話かを明確に予告しないと聴衆は不安になる
イントロで話の方向性を定め、それを少し予告することをスピーチの用語でプレビュー(preview)と言います。当たり前ですが、イントロでしっかりプレビューされないスピーチは、聴いていて不安ですしモヤモヤします。
あなたの話を聞くためにお金を払って参加するイベントなら、多少モヤモヤさせても聴衆はしっかり耳を傾けてくれるでしょう。でも実際には、多くの場合、聴衆はあなたの話にそれほど関心はありません。ゆえにイントロで明確に方向性を示し、聴衆に対して「こんな話をするから聴いてね」という気持ちを伝えるのが聴衆への配慮になります。
プレビューの方法で迷ったときは、ぜひイントロの最後で"Today, I'm going to talk about ..."と言ってください。こんなことをわざわざ言わなくてもよいという声もありますが、明解に表現することが最優先であることに異論はありません。こう宣言すれば、話者と聴衆は一瞬で同じ方向を向きます。
カッコいい表現より分かりやすい表現を心がけて
"I'm going to talk about ..."や"I'm going to discuss ..."などの「ベタな表現」が恥ずかしいと思う人も、まったく心配する必要はありません。簡単かつシンプルな言葉で、誰にでも分かるように伝えることは、スピーチにおける大原則です。
ちなみに私の研究室の学生も、まさにこの「ベタな表現」を使いますが、全国の英語スピーチコンテストで普通に入賞して帰ってきます。問題は、ベタな表現かどうかではありません。言葉がちゃんと伝わるかどうか、です。
スピーチに慣れてくるほどに、ちょっとカッコいい表現を使いたくなるものです。そんな時こそ基本に忠実に。選ぶ基準は「分かりやすさ」であることを忘れずにいてください。シンプルであることは、最高の美学です。

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など