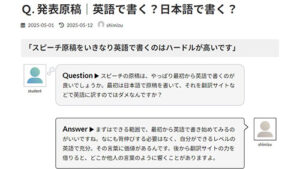課題解決力よりもまず「課題発見力」を育てる
現実的で説得力のある解決策を、聴衆への「お土産」にする。
※これは教員向け(教え方)の記事です。

説得型スピーチ(persuasive speech)の指導は、学生に社会問題を発見させるプロセスから始まります。みずから課題を発見しなければ、その先にある課題解決(solution)を語れないからです。近頃は「社会人基礎力」の文脈で課題発見力の重要性が注目されていますが、課題発見力や課題解決力の強化は、英語スピーチ教育が得意とする分野です。
社会と向き合うことから始めるスピーチ教育
説得型の英語スピーチにおいては、社会における問題提起(課題発見力)とその解決策(課題解決力)は常にセットです。このことは、スピーチの経験者なら当然に知っていることですが、初学者にはピンとこない感覚です。
まず、スピーチやプレゼンで解決策を提示するための「社会問題」と言われても、なかなか例を出せない学生がいます。大学生でもそうですから、高校生であればなおさらでしょう。裏を返せば、それほど日常生活において社会との接点が希薄だということです。
かつてテレビが茶の間の主役だった時代には、社会情勢の変化や社会で起きている諸問題については、テレビという共通の手段を通じて皆が自然に触れていました。それがスマホ中心の個の時代となり、社会問題は「自ら求めなければ得られない知識」となっている現状があります。
教員からすればスピーチ指導の"前段"がひとつ増える感覚になりますが、まずは社会に向き合うことの大切さから指導をする必要があります。課題発見力が養われてこそ、その先の課題解決力を発揮できるからです。
社会問題の多彩さを教えるのもスピーチ指導の役割
社会問題にも様々な種類がある、ということに気づかせることも大切です。「近所のゴミのポイ捨て」という身近なものから、ゴミはゴミでも「宇宙ゴミ」のように自分ではどうしようもない大きな問題まで、実に多彩。それらをすべて「社会問題」とひとまとめにするのはやや強引ですが、まずはブレインストーミングとして「どれも社会問題の仲間」と定義して、ひとつでも多くの社会問題に目を開かせる工夫が必要です。
その手段は、ニュースやネット記事から探させても良いですし、身の回りを眺めつつグループディスカッション等を通じた意見交換から気づかせても良いでしょう。みずから考える経験の中から「そういえばこれも社会問題かも」といった気づきが生まれます。
社会問題の存在を意識させることができれば、先ほどのゴミの例のように、それぞれの問題には原因や解決に程度(レベル)の差があることを指導します。「近所のゴミのポイ捨て」と「宇宙ゴミ」を、同列に扱うことはできないからです。
「自分で解決できるもの/できないもの」「政府主導の解決努力がいるもの」「国際協力が必要なもの」「それらのいずれでも困難そうなもの」など、課題を任意のレベルに分類するのも良い方法です。この課題レベルの違いは、課題解決の難しさに影響を与えます。
近所のゴミのポイ捨ての原因は何か?
説得型スピーチの要は、具体的な解決策にあります。社会における何らかの課題が発見できたら、その解決のための方法を考えます。その課題を引き起こした原因の考察結果に応じて、おのずと解決策は変わってきます。たとえば「近所のゴミのポイ捨て」の原因として、次のような例が挙がったとしましょう。
▶ ゴミのポイ捨ての原因(例)
(1) 当事者のマナーの欠如
(2) 近所のゴミ箱の不足
(3) コミュニティ全体の環境意識の低下
(4) 誰もが見て見ぬふりをする無関心さ
(5) ゴミそのものが発生する要因
原因が想定できれば、それぞれに対応した課題解決の方法が議論できます。上記(1)~(5)の原因に対応した解決策として、以下のような例が挙げられます。
▶ 各原因に対応した解決策
(1) 学校・会社・家庭でのマナー教育を実施する。
(2) ポイ捨てが多い場所にゴミ箱を設置/増設する。
(3) 自治会や地域の会合でポイ捨て問題を議論する。
(4) ポイ捨てをする人にみずから声をかける。自分も率先してゴミを拾うと宣言する。
(5) 捨てられるモノ(包装容器等)自体がゴミになりにくい製品開発を呼びかける。
上記の(5)は少々特殊な解決策に見えますが、この成功例として「缶飲料の飲み口」の事例があります。缶飲料の飲み口にはプルタブが付いていて、現在は缶を開封してもタブが外れないステイオンタブが主流。しかし昔は缶を開ければタブが外れる仕組みだったため、無数のタブが路上や砂浜に捨てられて社会問題になっていました。それをステイオンタブの開発によって課題そのものを解決したのです。
具体的かつ実行可能な解決策を「お土産」に持たせる
解決策の検討においては、それらに実効性があるかを判断し、学生に助言を与えるのが教員の役目になります。いくつかの解決策の中から、より具体的(concrete)で、より実現可能(feasible)なものを選び、それを解決策として提示するのがスピーチの基本的な考え方です。
中には、国や政府レベルでしか解決できない問題もあるでしょう。その場合でも「何か自分たちにできることは無いか」と問い続ける視点を失わないように指導してください。私の研究室では、そうした身近な解決策を(聴衆への)「お土産」と呼んでいます。スピーチを聞き終わったあと、何か自分が家に持ち帰れるお土産が無ければ、聴衆はその問題提起を簡単に忘れてしまいます。
課題解決力に先立つものが課題発見力です。発見した社会問題とその解決策がセットになって初めて、説得型の英語スピーチは成立します。まずは学生に社会問題を意識させ、その多彩さと課題レベルの違いを感じさせて、解決策を考えさせる。この一連のプロセスはスピーチ指導の枠を超え、学生の社会性を養う教育機会となります。
スピーチ教育を通じて学生が社会との接点を拡げられるよう、ぜひ積極的に助言を与えてください。先生方の社会経験に基づく視点は、先生方自身には平凡に感じられることでも、学生や生徒にとっては目新しい気づきになります。

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など