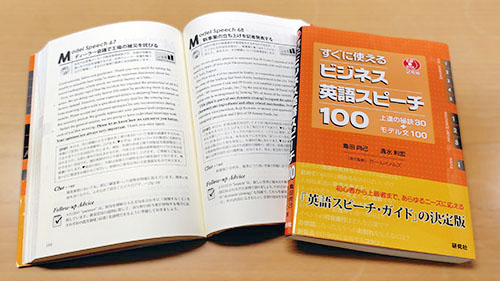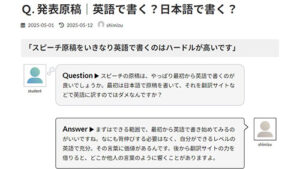ピアノで歌う、スピーチで語る、の共通点に学ぶ「スピーチの豊かな語り」
原作者のメッセージを表現する「想い」と「技術」の共演

楽器のレッスンでは演奏者の感情表現を「歌う」と表現するようですが、この「歌う」は、スピーチでいう「語る」に通じるものがあります。音楽でいえば楽譜以上の、スピーチでいえば原稿以上の表現力が、演奏者や発表者には必要なのでしょう。
自分の原稿なのに自分の言葉にならないもどかしさ
スピーチ原稿が完成しても、それが本当に自分のスピーチに成熟するにはあともう少しかかります。原稿には自分自身の言葉が並んでいるはずなのに、読んでみるとどうも自分の言葉のように響かないというもどかしさ。これはスピーチに取り組む誰もが最初に感じることです。
このもどかしさを分解すると、ふたつの要因があります。まずは純粋に「なめらかに発音できない」という英語的な要因。そして、原稿の言葉に「最適な感情を乗せられない」という感情的な要因です。どちらが苦手でも、結果的にうまく「語れない」ということになります。前者の「英語的な要因」の改善法は【100本ノック】のブログ記事で説明していますので参考にしてください。
スピーチ原稿の発音練習は、新しく楽器を始めた人が音符を追って音を出している状態に似ています。単に音読の練習をしているだけでは、話者の思いを十分に表現できているとはいえません。感情が込もった語りを身につけるには、何度も原稿をしっかり読み直し、自分の気持ちを声の強さ・抑揚・速度等の変化に反映させる練習が必要です。
同じ楽譜でも、演奏者がどう表現するかによってその曲想は大きく変わります。スピーチもまったく同じで、それがたとえ自分の原稿であっても、原稿に込められた気持ちをきちんと口頭で表現(再現)できて初めて、スピーチ本来の意図した感情が聴衆に伝わります。
自分はどんな気持ちを表現したいのか、をいつも確認する。
楽器で歌うのもスピーチで語るのも、そもそも自分がどんな想いを伝えたいのかを自分自身が理解することが肝心。スピーチ原稿が完成したら、ひとつ一つの文章で伝えたい気持ちを丁寧に思い起こして(時に書き出して)、その気持ちを伝えるように誠実に語ってみましょう。それがデリバリー(delivery)練習の初めの一歩です。
デリバリーというと、つい大げさな表情やジェスチャーを使う人がいますが、それほど大げさな表現が必要な場面はそう多くありません。ff (フォルテシモ)が延々と続く音楽は、聴いていてしんどいですよね? それぞれの文章を誠実に語って、結果として緩急のある感情表現ができるのが理想的です。最終はうまくいかないかもしれません。でも丁寧に気持ちを伝えることを意識して練習するほどに、少しずつ感覚が掴めてくるはずです。
私の研究室では、スピーチやプレゼンテーションの練習で「もっと語って!」という言葉が飛び交います。「読む」から「語る」段階、そして「感情を伝える」段階へと、語りが上達するにつれ、スピーチはどんどん自然になっていきます。
歌うことと語ることは、音楽とスピーチの基本的な共通点です。機会があれば、ぜひクラシックコンサートにも足を運んで、感情表現の幅を拡げてみはいかがでしょうか。一見遠回りのようですが、いずれスピーチの上達につながります。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など