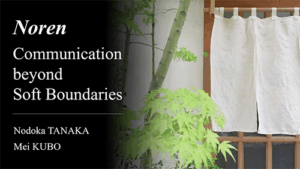学内大会運営|開催のたびに所期の目的を振り返る
目的が明確であってこそ意味を持つ中学校・高等学校の学内コンテスト
※これは教員向け(教え方)の記事です。

日頃の英語学習の成果を顕彰する学内開催の英語スピーチコンテスト。毎年の恒例行事として定着している学校もあるでしょう。運営担当の先生方にとっては開催の都度、所期の開催目標を振り返り、時に慎重な調整を試みることも必要になります。
学内大会と学外大会では異なる大会趣旨や審査基準
恒例行事として繰り返し運営する英語弁論大会であっても、そのコンテストが何のために開催されているかを意識することは意味があります。
中学校や高等学校の学内大会は、日々の英語授業での学修成果を実践的な運用の観点で評価する「教育色の強い行事」であることが多いようです。その場合には、口頭での英語表現力や発表技術(delivery)に主眼を置いた審査基準が設定されます。
ところが、それがオープン大会(学外主催の大会)になると、一転してスピーチの「総合力」が評価されます。審査は内容(contents)が60%~70%を占める「内容重視型」となり、単に英語が上手というだけでは入賞はできなくなります。
愛情を注いで指導した生徒が学外大会に出たとたんに入賞できなくなるのは、それぞれの大会の目標設定や指向性が異なるからです。この違いが「あの入賞者よりウチの生徒の方が英語が上手だったのに」というモヤモヤした気持ちを生むモトなのです。
審査基準の見直しはコンテスト自体の趣旨に影響する
学外大会のトレンドに沿って、学内大会の審査基準を内容重視に変更する場合、注意すべき点が2つあります。ひとつは、日頃の英語授業だけでカバーできない領域が審査の多くを占めること。もうひとつは、内容偏重型だと英語がうまいだけでは入賞が困難になるため、その生徒が自信を失うリスクがあることです。
前者は、スピーチの内容を重視した指導が英語授業(あるいは連携する国語授業)で展開されている場合には問題ありません。しかし実際には、そこまでをすべて授業でカバーするのは非現実的です。ゆえに安易に内容重視の審査基準に変更すると、日頃の英語授業の運用成果を競うとした所期の目的が失われます。そしてこれが後者の「自信を失う原因」につながります。
こうした問題を回避するには、学内大会の運営目的を再認識することです。純粋に「英語授業の学び」の延長としてのコンテストであれば、英語重視の暗唱(recitation)や音声解釈表現(oral interpretation)をコンテストに導入するのも一案です。同時に、スピーチ部門では審査基準で「内容」が50%を越えないようにする配慮も必要です。
大切なのは、所期の開催目的を思い返すことです。審査基準を見直すということは、コンテストの開催目的にも影響を与えます。コンテストの運営は、毎年繰り返すほどにルーチンワークとなり、その存在意義を忘れがちです。お忙しいとは思いますが、コンテスト担当の先生方には現状の審査基準と大会運営の目的がリンクしているかを、時に振り返っていただくことをお勧めします。
学内大会で内容偏重型の審査基準を設ける意義は?
学内大会の審査基準で、(学外大会並みに)「内容」に60%以上を配当することを否定はしません。内容重視の学内大会を実施する意義は、生徒の将来の活躍を「今から」支援できる点にあります。
内容重視の審査基準があるのは、中学生・高校生対象の学外大会に限らず、大学進学後に挑戦する各種大会でも同様です。それに備えて、今から、スピーチ本来の「社会との向き合い方」を問う弁論大会を中学校や高校の学内で開催することは前向きな意味があります。
大切なのは、学内大会の開催目的です。それが歴史ある恒例行事であっても、時折その意味を考え直すことは、生徒にとっても教員にとっても意味があるはずです。

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など