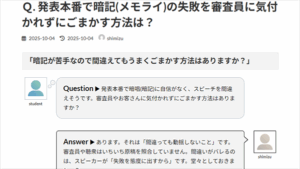スピーチ指導はどこに注力するか?英語力強化とスピーチ力強化の選択と見極め
学生のやる気と現在地を見極め、将来の可能性を拡げる。
※これは教員向け(教え方)の記事です。

学生の可能性を拡げる英語スピーチ指導には、2つのフェーズがあるように感じます。ひとつは「スピーチで英語力を伸ばす」実践。もうひとつは「英語力でスピーチを伸ばす」実践です。この片方で終わるか、あるいは前者と後者が理想的に連携し、一貫した成長を示すかは、本人のやる気も重要ですが、どこにどれだけの教育リソースを配分するかという教員の判断が重要になります。
【フェーズ1】英語力を伸ばす指導:リソース配分の留意点
第1のフェーズとは、「基礎的な文法や発音に課題がある」「英語で自分の意見をスムーズに構成できない」「声に自信がない」といった学生の現在地を示しています。
スピーチコンテストへの参加においては、学生(生徒)に対して様々な指導が必要になります。全国大会の常連を輩出するような一部の学校を除き、多くの場合は「スピーチを媒介にして英語力を伸ばす」というフェーズから指導が始まるケースが多いのではないでしょうか。
私の研究室では、お蔭さまで毎年全国入賞者が出ていますが、それでも受賞者のほぼ全ては「英語力」を伸ばすフェーズからのスタートです。基礎的な英語学習の延長戦のような練習が続き、発音から表現技法に至るまで、その多くが基礎からの見直しです。教員にとっては、時間も労力もかかる取り組みです。
過去記事「学生の上達速度と到達レベルを予測し、スケジュールと目標を設定する」にも書きましたが、学生が「英語力を伸ばすフェーズ」にある場合、どこに指導目標を置くかを意識する必要があります。学生本人に明かす必要はありませんが「本番までの残された時間で、その学生がどこまで伸びるか」を見極め、何に注力すべきかを教員が考える必要があるということです。
もちろん、スピーチの指導ですから、スピーチの内容や構成を指導することは欠かせません。ただ、人前での発声や、円滑なコミュニケーションが可能となるレベルの発音、安定したイントネーションの指導にあまりに時間がかかることが予見される場合、「スピーチ本体」に指導時間を割きすぎると、結果的に「伝わる」スピーチにはなりません。残念ながら、そのようなミスマッチは時折発生します。
英語力を伸ばすフェーズにある学生に対し、どこまで「スピーチそのもの」の指導にリソースを割くかは、なかなか難しい判断になります。一方、仮に「英語力の向上」を重視した指導プランで進めるとしても、学生本人のプライドもありますので、基本的には教員の心の中だけでリソースの配分を判断し、指導あたることになります。(この点、判断にお困りのことがあればご遠慮なくご相談ください。)
【フェーズ2】スピーチ力を伸ばす指導:本質への注力
第2のフェーズとは、「日常的な会話や誤解のないコミュニケーションは可能」「英語力より"何を語るか"に課題がある」「自分の主張を論理的に構成する経験が不足」といった学生の現在地を示しています。
もともと最低限度のスムーズなコミュニケーションが可能な場合や、上記の「英語力を伸ばすフェーズ」を経由して英語力を身につけた学生の場合は、その英語力を活用して「スピーチ力を伸ばすフェーズ」に取り組むことになります。
このフェーズでは、コンテンツを中心とした「思考力や人間的な深み」が試されること、表面的な英語力だけでは入賞は狙えないことなど、英語スピーチの本質的なあり方を学生に理解させる必要があります。論理的・批判的な思考力や、課題発見・課題解決力、さらには説得力のある話の構成力が試される点の指導は欠かせません。
とりわけ、このフェーズから練習が始まる学生は、比較的英語力に自信があり、それゆえにスピーチの内容よりも、デリバリー(発表技術)や発音の美しさを前面に押し出してしまうことが多い点にも注意が必要です。
そのような学生に対しては、語りや発音の指導は「基礎練習」として継続しつつも、メインはスピーチのテーマ設定や解決策などの「説得型スピーチの基本構造」を磨く工程に指導リソースを割くのが望ましいです。なぜなら、最終的には、「スピーチとして理想的な論旨の構造」が満たされなければ、どれだけ英語力があっても話者の真価を発揮できないからです。
英語力があり、やる気もあって、スピーチに挑戦したいという学生が現れること。さらにその学生に、情熱をもってスピーチを指導できる教員が出会うということは、本当に恵まれたご縁です。まずは「スピーチとは何か」という原点から、スピーチに関する先生方の知見を学生と共有いただければと願っています。
究極的に「学生の未来の可能性を拡げる」目標は同じ
どちらのフェーズから始まっても、またふたつのフェーズを連携して指導できたとしても、スピーチ活動を通じて学生の可能性を拡げるという教育目標は同じです。
スピーチ活動を通じた教育は、英語力やスピーチ技術に留まりません。私自身もこれまでに多くの学生を指導してきましたが、「スピーチの練習を通じて豊かな声を手に入れた学生」が堂々とした自信を獲得したことなど、印象に残る思い出はたくさんあります。その学びの価値は、コンテストで入賞できたかどうかとは無関係です。
ぜひ、ご縁のあった学生それぞれの現在地を見極め、先生と過ごす「スピーチ練習の時間」を通じて、そこから最も価値のある学びを提供していただければ幸いです。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など