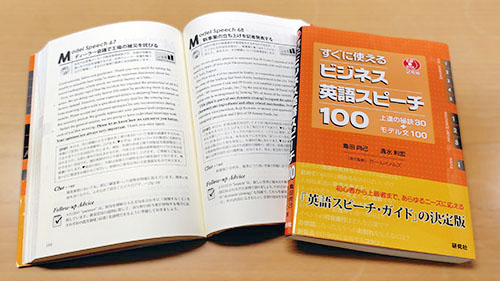Q. スピーチで話者の気持ちを伝える「語る」とはどういう読み方?
「気持ちを込めても気持ちが伝わらないときはどうすれば?」

Question ▶ スピーチを通じて自分の気持ちを伝えているつもりなんですが、聴き手にはなぜか「棒読み」に聞こえます。どうしたらいいですか?
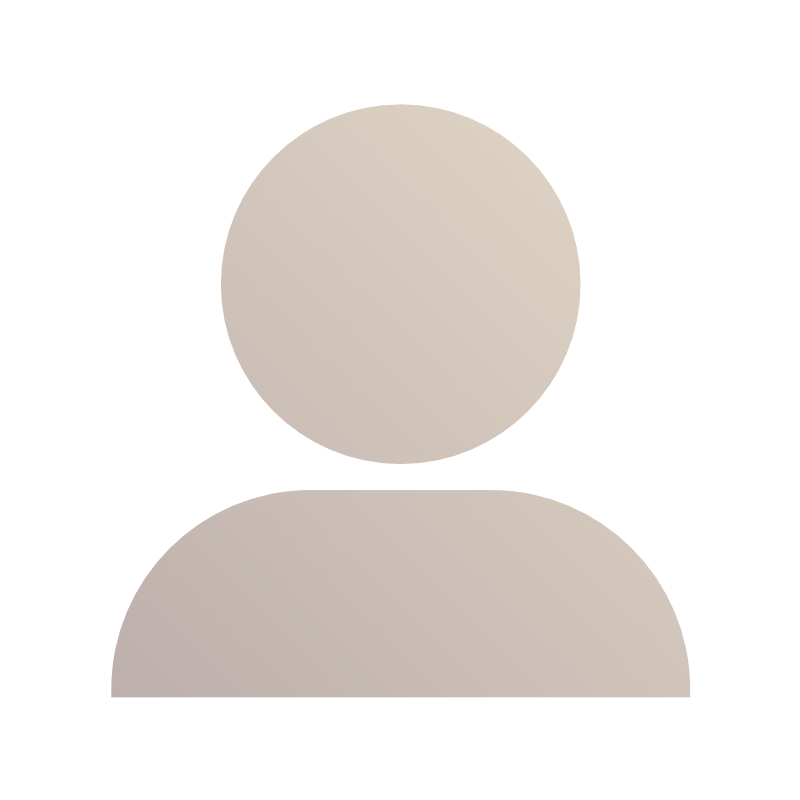
Answer ▶ スピーチでは、「語る」という意識を持つと良いです。話している一つひとつの単語に、きちんと自分の思いが載っているかを確かめて話してみましょう。
音読の声は「音声」。語りの声は「感情」。
初めてスピーチに取り組む人が最初に直面するのが「語る」練習です。意外に思われるかもしれませんが、「語り」の上手さは、「音読」の上手さとは実はそれほど関係がありません。
音読が上手でも「語り」ができていない人はとても多くいます。一方で、音読がぎこちなくても「語り」は十分に伝わるスピーカーもいます。つまり、「語り」の質を支えているのは、一つひとつの言葉の奥にそのスピーカーの感情を感じられるかということです。
簡単に表現するなら、音読の声は原稿を音にした「音声」。一方、語りの声はそこに「感情」が感じられます。いわゆる「棒読み」という指摘を受けるのは、まだスピーチが「音読」のレベルに留まっていることの裏返しです。
最初の一歩は、気持ちを「2割増し」にして丁寧に語る。
4分程度のスピーチであれば、概ね400語程度の英単語が原稿に並んでいます。この中には、不必要な単語はありません。どの単語も、話者の気持ちを伝える"重要な役目"があります。あとはその「重要な役目」を話者本人が意識し、きちんと口頭で再現できるかにかかっています。
棒読みから卒業するためには、まず自分の気持ちを「2割増し」にして、原稿を語ってみましょう。慣れるまではこれだけで気恥ずかしさがあるかもしれませんが、聴衆が話者の気持ちをしっかり理解するためには、当然に話者も自分の気持ちを「しっかり伝えきる」努力が必要です。
嬉しい時には嬉しい声で、嬉しい表情。悲しい時には静かな声で、寂し気な表情。気持ちが高ぶるときには大きな声で、真剣な表情。そうやって、原稿の上を流れていく単語を都度丁寧に意識をすることで、棒読みは次第に脱却されていきます。
ぜひその練習のプロセスは録音・録画をして記録を残し、時折それを見直してみてください。少しずつでも、自分の成長を感じられるはずです。時折、自分自身を褒めてあげながら、気持ちを言葉に乗せていきましょう。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など