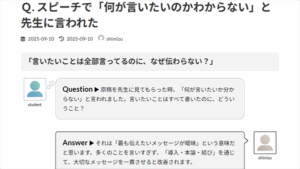スピーチコンテストの審査員を発表開始2秒で不安にさせる3つの方法
スピーチの良し悪しを決める「悪し」を避けて「良し」にする!

英語スピーチやプレゼンコンテストで、最初の数秒間は結果を大きく左右します。もし冒頭で審査員が「このスピーチ、大丈夫かな?」と感じると、ほぼその不安は的中します。この記事では、私がスピーチコンテストの審査員を務めてきた経験から、冒頭で避けるべき3つの要素と、好印象を与えるための具体的な方法を解説します。これらのポイントを押さえて、最高のスタートを切りましょう!
【その1】過剰な演出やデリバリーは、不誠実のもと。
スピーカーが演台に上がり、司会者(MC)への挨拶が終わって、いよいよ本番。そこでいきなり舞台俳優のような「強い演出」が始まると、審査員は強い不安を感じます。よくあるのが冒頭から感情むき出しの「デリバリー」(声やジェスチャーによる表現技法)です。これは避けるべきです。
スピーチが始まった瞬間は、聴衆の「聞く体制」が整っていません。そんな時にいきなり「手を大きく広げるジェスチャー」や「大げさな笑顔」など、熱々の舞台演劇を見せられると単純にしんどいです。聴衆の心は次第に温めていくもの。自然な語りから入って、まずは「誠実な印象」を与えることに注力してください。
そもそも、大げさな演出は、スピーチのどの部分であっても避けるべきです。話者は誰も自分のデリバリーが「大げさ」だと自覚して発表することはないでしょう。それでも聴衆が「大げさ」と感じるということは、聴衆との間に一体感を創出できなかったということで、その時点で失敗です。
オープニングでの過大なジェスチャーも控えてください。ジェスチャーで目立つというのは、自分が特別なゲストスピーカーでない限り、危険なスタートになる可能性が高いです。大げさな身体表現は控えること。これはとても大切です。
過剰な演出を避けるためには、まず自然な語り口で始めましょう。挨拶や自己紹介は落ち着いたトーンで。身振り手振りは、話の内容に合わせた最低限のものからスタートし、聴衆との一体感が生まれてきたと感じたところで、徐々に表現の幅を広げていくのがおすすめです。大切なのは、誠実さが伝わることです。
【その2】爆速で話し始めると、聴衆は置き去りに。
開始冒頭からいきなり剛速球で言葉が次々飛んでくると、審査員はその勢いに不安を感じます。早口の語りは、物理的に聴き取りにくいですし、聴衆を置き去りにするリスクが高いです。
コンテスト本番は緊張しますから、誰でも早口になりやすい状況にあります。そんな状況にあって、そもそも「早口の傾向がある人」は、恐らく自分でも驚くほど早口になっていると思った方がよいです。特にスピーチの冒頭で聴衆を置き去りにしてしまうと、その後いくらゆっくり語り掛けても、聴衆はスピーチを巻き戻して聞き直すことはできません。
特に気を付けるべきは「英語が流暢な人」です。英語が流暢な人は、そもそも「1分あたりの発話量」(WPM: Word Per Minute)が多いので、それがさらに速くなるということは「1分あたりの情報量」が単純に増えます。情報力が増えれば、それに比例して、聴衆はスムーズな理解が難しくなります。
また、英語が流暢な人が早口でしゃべると、多くの場合、語尾の子音が飛んだり、二重母音が単なる長音に聞こえたり、発音の質が下がることがあります。そうすると、審査員には「無理して上手に話そうとしている」という印象を与えます。そんな誤解を生まないためにも、落ち着いて話し始めてください。
早口を避けるためには、とにかく冒頭をゆっくり語る練習をしましょう。その際、必ずスマホなどで録音・録画をして、客観的に自分のスピードをチェックすると効果的です。大切なオープニングだからこそ、間(ま)を効果的に使うことで、聴衆がスムーズに情報を整理できるようになります。
【その3】小声の語りは、感情表現の幅を狭くする。
話者がMCに謝辞を述べる時点で「声が小さいな」と感じたスピーカーが、スピーチでも小さな声で話し始めると、審査員は不安になります。
声が小さくても、誠実な感情表現ができていれば、小さな声は「その人の個性」ですから問題ありません。ただ多くの場合、声が小ささは「自信の無さ」や「練習不足」を感じさせたり、結果的に感情表現が不十分だと受け止められる場合があります。
音響技術の分野に「ダイナミック・レンジ」(dynamic range)という言葉があります。これは、特定の音響機器が扱える音の大きさの「振り幅」を指す言葉です。簡単にいえば、どんな小さな音から、どんな大きな音までを扱うことが出来るかという指標です。
スピーチやプレゼンにおいても、この「ダイナミック・レンジ」という概念はとても重要です。その理由は、そのスピーカーが持つダイナミック・レンジ(振り幅)が広いほど、声による表現力の奥行きが拡がるからです。逆に声が小さい話者は、もともと「狭いレンジ」で勝負することになるので不利になりやすいということです。
「プレゼンテーション用の豊かな声」(presentation voice)を作るには、普段よりも少し声を張る練習をしましょう。無理して大声を出す必要はありません。今より少しだけ「ダイナミック・レンジ」を拡げることを意識するだけで、スピーチの出だしに力強さが加わるはずです。
リスクを減らし、安定したスタートで好印象を獲得!
上記の3つの要素を避ければ入賞できるというほど、コンテストは単純ではありません。しかし、良し悪しを決める「悪し」が無くなれば残るは「良し」のみ、という理屈は理論的には成立します。少なくとも、冒頭から審査員に悪い印象を与えて、それがスピーカーの不利益になることは避けましょう。
上の3つは、どれも「日頃の練習によって矯正可能なもの」です。ぜひ動画を撮影してチェックしたり、信頼できる先生に見てもらうなど、改善に努めましょう。コンテスト本番の「出だし2秒」で、ぜひ最高のスタートを見せてください!
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など