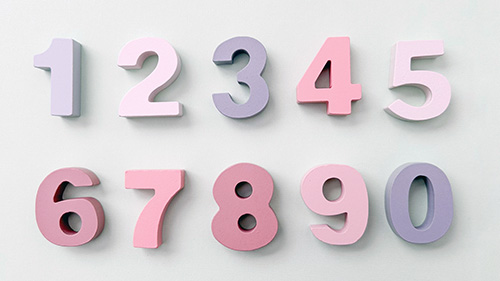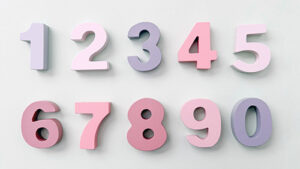英語スピーチを論証する「起証結」の3段構造には「転」が無い!
本論の役割は例示と論証だと意識しよう

英語スピーチの話題展開は、起承転結ではなく「起-承-結」だと過去の記事「英語スピーチやプレゼンでは起承転結を避ける」で説明しました。今回は、スピーチの本体(body)を成す「承」は、実は「証」(証明と論証)である、というお話です。
具体的な例を示して証明することの大切さ
ブログ記事「サンドイッチ型の3層構造に慣れよう」で紹介したとおり、英語スピーチは「起」(intorduction) →「承」(body) →「結」(conclusion)の3層構造で構成されます。その中で最も大きなボリュームを占めるのが「承」、すなわち本論(body)です。bodyの主な役割は、様々な角度から論点を支える例を挙げ、主張が正しいことを証明すること。その意味で、bodyの「承」は証明と論証の「証」であるともいえます。
情報提供型のinformative speechであれば、bodyの役割は、具体例を示して話の真実性を証明することです。好きなスポーツ(たとえばテニス)がメイントピックであれば、以下のような要素がbodyに入ります。
- テニスを好きになった理由
- 好きなテニス選手
- 最近出場した試合
- お気に入りのテニス用品
- クラブ活動での思い出や出会い
- テニスに学んだ教訓 ... など
説得型のpersuasive speechの場合はどうでしょうか。たとえば日常的な運動を日々の生活にとり入れることを訴えるスピーチの場合、bodyでは次のような例を示して論点の重要性を論証するでしょう。
- 運動をすることによる健康効果データ
- 運動不足に伴う生活習慣病のリスクの程度
- 実際に運動習慣が無い人の割合や主要な年齢層
- 気軽に実践可能な日常運動(エクササイズ)の例
- 日常的な運動をした場合の費用対効果
- 運動を[した/しなかった]場合の精神的ストレスの検証データ ... など
情報提供型も説得型も、どちらも論点を支える具体的な事例が主張の正当性を論証しています。これが「承」(body)を「証」と呼ぶ理由で、スピーチが「起証結」を構成するゆえんです。
客観的な事実やデータで論証する習慣をつけよう
本論(body)における論証で大切なのは、実際に起きた事実や統計データなどを示すことです。具体例を挙げる際も、そのイメージを聴衆が思い描けるほどに具体的なものだと論証の力は強くなります。
究極の具体性は、数字です。具体性を先ほどの例で表現するなら、テニスクラブに所属をしていたメンバーは「何人」で、その規模はテニスコート「何面」で、自分が愛用しているラケットは「何本」で、といった数字を挙げること。運動習慣を勧めるスピーチであれば、運動と健康に関する医療データから、さらに具体的な数値が出せるでしょう。
日頃の会話の中においても、根拠や事例を例示する習慣をつけてみてください。慣れるほどに、スピーチやプレゼンでの説得のコツがつかめるようになります。
ここで触れた「起-証-結」型の構成法については、『すぐに使えるビジネス英語スピーチ100』の Speakers' Tip 11 で詳しく説明しています。本書をお持ちの方はご参照ください。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など