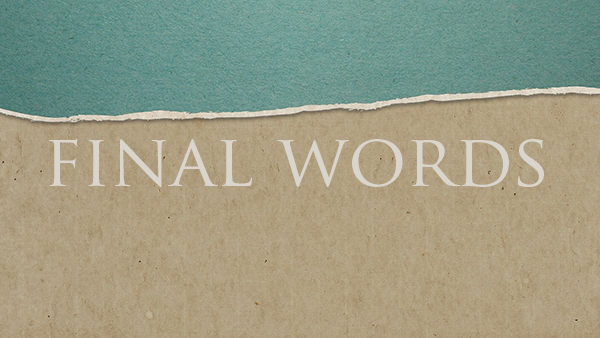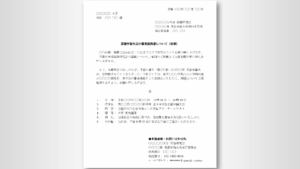【 トンネルの法則 】スピーチの最初と最後を完璧にすれば中盤の印象は補われる
入口と出口で見える景色がトンネル全体のイメージを決定づける

スピーチやプレゼンとトンネルはとてもよく似ています。トンネルで記憶に残るのは入口と出口の景色。中は真っ暗です。スピーチもまた、最初と最後の段落はずっと聴衆の記憶に残る重要な要素になります。妥協のない練習を経て、出だしと終わりが完璧に演じられれば、中盤の印象は「始まりと終わりの記憶」によって自然と補われます。
出だし ▶ 一語の妥協も許さない完璧なスタートを
「終わり良ければすべて良し」という諺がありますが、英語スピーチやプレゼンテーションに関しては「始め良ければすべて良し」です。演台に立った瞬間からスピーチの出だしを経て、第一段落が終わる最初の30秒~1分間は、スピーチの印象を決定づける影響力があります。
ゆえにコンテストや大切なプレゼン本番では、この出だしをとにかく(自分の中で)完璧と言えるまでに仕上げてください。最初の段落(introduction)では、単語ひとつの発音もおろそかにせず、語りのスピードや間(ま)の取り方、大切な単語の強調具合、笑顔や姿勢などの見栄えに至るまで、一つひとつの要素を徹底して磨き上げることが重要です。
出だしの質にこだわるのは、最初で崩れたイメージを後から取り返すのは極めて困難だからです。最初に「あ、なかなか上手だな」「いいスピーカーだな」という印象でスタートできれば、中盤で多少つまずいても、最初の好印象によってミスはカバーされます。とにかく第一段落の仕上げに魂を込めることです。
実際の練習においては、「最初の段落が完全に納得できるまで第2段落には進まない」くらいの覚悟と気迫で練習に臨むのが理想的です。そのような情熱は、必ず発表冒頭のインパクトとなって強いスピーチを後押しします。
終わり ▶ 聴衆の耳にエコーする美しさやインパクトを
最終段落から退場までの終盤は、「終わりよければ~」の諺どおり、文字通り発表全体の印象を確定させます。過去記事「辞世の句」での説明にある通り、話者の魂を語り切って、聴衆の耳にこだまする気持ちの良いエンディングを演出する必要があります。
基本的に最終段落(conclusion)では、新しい話題が持ち出されることはありません。それまでに論じた内容を改めて整理・統合したメッセージが中心になるはずです。ゆえにその重要な思いやキーワードなどをしっかり聴衆の脳裏に刻み込むことを目指し、繰り返し丁寧に練習することが重要です。
終わり方は、スピーチによって様々です。気迫の込もった情熱的なエンディングもあれば、静かな呼びかけでメッセージの深刻さを表現する方法もあります。どちらのやり方であっても、その意図がきちんと聴衆に伝わるように、何度も録音・録画をしてチェックするようにしてください。
発表練習の優先順位も「サンドイッチ形式」で
多くの場合、練習時間が潤沢にあるケースは少ないでしょう。そんな時こそ「出だしと終わり」を集中的に練習し、出だしで「上手な語りだな」と思わせ、終わりで「いいスピーチだったな」と思わせれば、スピーチ全体の「印象づくり」は成功です。
もちろん、スピーチ中盤のデリバリー(発表技術)をおろそかにして良いはずはありません。しかし、限られた練習時間を考慮すれば、現実的な優先順位として、「聴衆の心をつかむ出だし」と「メッセージを締めくくる終わり」に時間を割くことには十分な合理性があります。
優れたスピーチの構造は「サンドイッチ形式」をとりますが、その語りにおいても「はじめ」と「おわり」が万全になれば、スピーチ全体の印象をサンドイッチ式に強化できます。磨くべきは、トンネルの入口と出口です。ぜひ覚えておいてください。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など