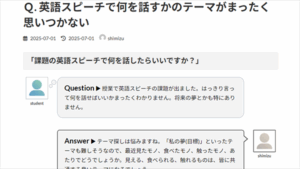【 あじさい 】スピーチの色彩を決めるのは花びら単体か房全体か
スピーチ全体としての「見え方」を意識する大切さを知ろう

初夏を彩る紫陽花。スピーチ全体を通じて受ける印象は、このアジサイの房に似ています。花びらが単語、一つひとつの花が文章、それらが集まった房がスピーチといったところでしょうか。一見単一色に見える紫陽花でも、その中にある花びらの色は微妙に違います。それらが全体のバランスを保ちながら、ひとつの房を作り上げている姿はスピーチにそっくりです。
文章や単語にこだわるよりも、全体的な色調を大切にする。
スピーチを指導していると、「ここはどう言ったらいいですか」「この表現で伝わりますか」といった質問をよく受けます。英語教員としては、もちろんそれぞれの質問に答えていくわけですが、一つひとつの小さなパーツにこだわるよりも、全体を通じて与えるメッセージとその印象のほうが実は大切なのです。
紫陽花は、個別の花と、集合体としての美しさのバランスが絶妙です。鮮やかな単色に見えるあじさいの房も、よく見ると、一つひとつの花びらには濃淡があることに気付きます。時に、白っぽかったり、色が未熟に見える花びらもあります。それでも房全体で見ると、それらの色の違いが全体の立体感を演出しています。
花びらが単語、花が文章、房がスピーチ全体として考えてみれば、スピーチはとても紫陽花に似ています。時に英語としては未熟な表現でも、それが全体としての美しさや誠実さを演出することはよくあります。逆に、全部が完璧に同じトーンで統一されれば、深みや立体感のない、インパクトだけの印象が残るでしょう。
英語スピーチを指導する際に、私はよく「この言葉は色目が違う」「この表現はちょうどいい色合いだね」といった言い方をします。振り返ってみれば、ひとつひとつの言葉と全体の色調や調和を無意識に判断しているように感じます。
それぞれのパーツが不揃いであるがゆえの、全体としての立体感や美しさは、スピーチメーカーとして紫陽花に学ぶきポイントです。またスピーチの指導者としても、最終的に一人ひとりの「学生らしい言葉」をきちんと活かした表現を指導し、それを原稿に刻んでいくことが大切です。
多少色合いが不揃いでも、全体として美しければ良い。
冒頭の話に戻りますが、スピーチを書く人にとって、細かな英語の出来や、その先にあるレトリックの技巧さは、後回しで構わないものです。まずは、スピーチ全体を通じて何を訴えたいか。この点をクリアにして心に刻み、聴衆を思い浮かべながら言葉を運ぶことが何より大切です。
逆にいえば、最初から最後まで、ずっと単調で画一的な表現が続くと、それは全体としての立体感や深みを失うことにつながります。
たとえば、伝えたい主張を何度も繰り返したり、聴衆を悪者にして上から押し付けるような表現が続いたり、あるいは「〇〇はこうあるべき」といった絶対正義を振りかざしたり。これらは、ありえないと思われるかもしれませんが、スピーチコンテストの審査員をしていると、こうしたスピーチに出会うことは少なくありません。
諸々の委細にとらわれず、全体としての美しさを尊重することは、聴き手にとっても嬉しいはずです。紫陽花畑に行って、花びらを一枚一枚確認する人はいません。全体としてどうありたいか。全体として聴衆にどんな印象を残したいか。紫陽花から学ぶべきスピーチの大切なポイントでしょう。
個々の完璧さよりも、多少トーンが不揃いでも、全体として調和した美しさを見せることが、聴き手の心に深く響くスピーチを創り出す秘訣です。次に紫陽花に触れる機会があったら、そんな「スピーチの色彩」に、ぜひ思いを馳せてみてください。

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など