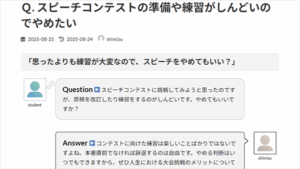大学生らしい英語スピーチの発表は、掘りの深さと角度で差をつける。
どこを掘るか、どこまで掘るか、のバランス感覚をつかむ。

スピーチコンテストでは「大学生らしい素晴らしいスピーチだった」というコメントを聞くことがあります。この「大学生らしい」とは何でしょうか? 簡単に言えば、大学生らしさはスピーチの「深さ」に表れます。そこで問われるのは、「どこを掘るか」という視点の面白さと、「どこまで掘るか」という分析の深さのバランス。大学生らしい、深みのあるスピーチとは何かを考えてみましょう。
「どこを掘るか」を間違えると、スピーチは不利になる。
乾いた土にシャベルを突き刺す時、ザクっという気持ちの良い音が聞こえます。この気持ちよさは、スピーチにも共通する感覚があります。スピーチを聴いていて、「そこを掘ったか!」という驚きの気持ち。さらには「何が出るだろう」という期待感。言うまでもなく、「どこを掘るか」はスピーチの成否を分ける大きなポイントです。
「どこを掘るか」というのは、いわゆる「目の付け所」です。誰もが知らない場所にシャベルを刺せば、会場には緊張感が生まれます。一方、誰もが聞いたことのあるテーマを掘り始めると、聴衆は「あぁ、またあの話か」と感じ、その後の期待感は一気に薄れてしまいます。
スピーチを大学生らしいものにするには、まずこの「目の付け所」が重要です。当然ながらスピーチはどんな話題でも展開はできますが、冒頭から聴衆の注目を獲得し、それを維持し続けるためには、ザクっという音を聞いただけで聴衆がハッとするような、「どこにシャベルを刺すか」という観点が欠かせません。
その最も簡単で効果的な「シャベルを刺すべき場所」は、誰もが聞いたことはあるけど深くは知らない領域です。これを見つけるためには、社会を深く考察し、日頃から問題意識をもつことが必要です。それを見つけるために試行錯誤したり、悩んだり、友人と相談をしたりといった誠実な姿勢から「大学生らしさ」が表れてくるのです。
単に「目の前に土があるから掘ってみた!」というのが中学生・高校生のスピーチだとすれば、大学生は彼らの視点を既に見越して、より高い場所から、シャベルを打ち込む「新たな場所」を探さなければなりません。過去記事「スピーチテーマを絞り出したその先に斬新な発見がある」を参考に、「見えてはいるけど、まだ掘削されていない」新しい場所を探してください。
「どこまで掘るか」が大学生らしいスピーチをつくる
次に「大学生らしい」スピーチに必要な要素が「どこまで掘るか」です。単に社会問題をレビューする表層的な考察でなく、その深層にある本質を掘り起こす緊迫感を感じられることが、大学生のスピーチには必要です。深く深く掘って、ゴンっと宝箱にシャベルが当たる感覚、と表現できるかもしれません。
私がスピーチコンテストの審査員として審査用紙にコメントを残す際、よく書き込む言葉が「もっと深く考えて」というメッセージです。深ければ良いというものではありませんが、問題を掘る深さは、その問題と向き合う本気度に比例します。「この話者はそこまで考えているのか」という印象を与えられるまで、自分のテーマを掘り込んでください。
「掘る深さ」と同じくらい大切な観点として「掘る角度」があります。同じ場所、同じテーマを掘っても、掘る角度によって、たどり着く先は変わります。問題を掘ってみて、本質的な問題に突き当たることができなければ、違う角度から検討をしてみることも大切です。
「掘る深さ」と「掘る角度」の両面で考える
「掘る深さと角度」について、ひとつ例をあげましょう。たとえば「乗客のイヤホンの音漏れ」を議論するとします。この時、「乗客のマナーの悪さ」という視点だけで語るのは、完全に表層的なスピーチになります。もし、それを「マナー」単独の問題と捉えてしまえば、それに連動する解決策は「マナー向上キャンペーン」のような平凡なものになるでしょう。これでは「大学生らしい」掘る深さが足りていません。
もう少し掘り下げてみます。そうすると、問題の原因として「学校や家庭での指導」を掘り当てるでしょう。それをさらに掘り下げると、「家庭での子育て」「学校での道徳教育」といった課題に行きつきます。それをまた、さらに掘り進めれば、「個人の自由を尊重する風潮と、他者への配慮の不均衡」という考察に突き当たるかもしれません。このように、掘る深さを増すことで、目の前にある何気ない問題の根深さに気付き、より本質的な発見につながります。
それでもまだインパクトに欠けると感じる場合には、さらに違う角度でも掘ってみるのです。同じ「音漏れ」の問題でも、掘る角度を変えれば、たとえば「他人に迷惑がかかる商品の販売活動」「聴力や健康への悪影響に対する意識の低さ」「趣味と配慮のバランス」といった、まったく違う原因を掘り当てることができるでしょう。
こうして発掘したすべての要素を複合的に組み合わせることで、最も鋭い「問題の本質」が追求できます。その実践力や提案力こそが、大学生らしいスピーチの「深み」を生むのです。
どこにスピーチの宝箱が埋まっているかは、場所を変え、深さを変え、角度を変えて、掘ってみないとわかりません。スピーチに対する一連の取り組み方からうかがえる、いち大学生の誠実な人柄(エトス)が、弁論大会の審査員の胸に響くということを忘れないでください。
■ 関連記事
▶ 説得の3要素「ロゴス・パトス・エトス」のバランスで英語スピーチに説得力を [リンク]
▶ 高校生の英語スピーチ、題材やテーマで差をつける「背伸び」の極意 [リンク]

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など