迷える学生を導く「言い切る指導」で英語スピーチへの関心を高める方法
答えのない答えを示す時こそ「言い切る愛情」で学生に接する
※これは教員向け(教え方)の記事です。
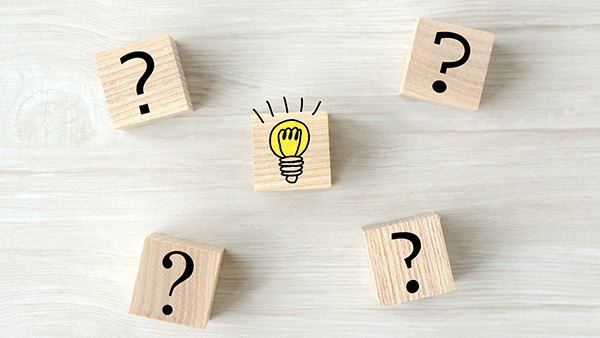
英語スピーチを指導する中で、「正解のない質問」にどう答えるべきか、悩んだ経験はありませんか? 学生の真剣な問いに対し、教員が「どちらでも良い」と回答することで、かえって彼らを不安にさせることがあります。学習者の成長を促しつつ、英語スピーチへの関心を維持・向上させるための「言い切る指導」の重要性を考えてみましょう。
なぜ「言い切る」ことが学生のやる気を引き出すのか
そもそも、前向きな関心がなければ質問は出てきません。その意味で、学生からの質問にはすべて意味があります。どの質問にも、きちんと回答を返すのは教員の基本的な役割です。
英語スピーチに関して言えば、英文法や用法など英語そのものに関する質問は、一応の「正解」があることが多いので比較的答えやすい部類です。一方、テーマや解決策に関する質問は「何が優れているか」の簡単な正解がないため、回答に苦慮するときがあります。
それでも学習者からの質問は、真摯にスピーチと向き合っていることの証です。「どちらでも構わない」「それは自分で考えて」と返してしまいたくなる場面でも、教員が何らかの答えを明示したうえで、最終的に学習者の判断を尊重するよう助言を与えることが必要です。そうすることで、スピーチ活動に対する学生のやる気やモチベーションを維持することができるからです。
答えのない質問に答えを出すには何らかの根拠を添えて
英語スピーチに関して最初によく聞かれる悩ましい質問は、「どちらの(どの)テーマがいいですか」です。この大きな質問を例に、考えられる回答のバリエーションを考えてみましょう。
1) どちらかの選択を迷っている場合
AかBのテーマで迷っている場合、「独自性」や「解決策の出しやすさ」の判断基準から、どちらが正解かを答えられる場合があります。どちらも大差ない場合には、「どちらでも好きな方で」と返したくなります。でもこのような場面では、既に本人の中ではどちらかに気持ちが傾いていることがあります。教員が本当に「どちらでも良い」と感じる時には、本人の意向を聞き出して、その選択肢を明示的に勧めるのが良いでしょう。
たとえば、学生にはこんな風にアドバイスをしてはどうでしょうか。「テーマAは珍しいテーマで独自性があるから聴衆の印象に残る一方、テーマBは具体的な解決策が出しやすいので、あなたの熱意や提案力が伝わりやすい。どちらが自分に適してると思う?」と一定の根拠を明示しながら、学生自身の意向や本心を尋ねてみるのも良いアプローチです。
2) いくつかの選択肢で迷っている場合
複数のテーマで迷っている場合、テーマ決定まで時間がある場合には、(1)と同様に、独自性と解決策の観点を指導したうえで、2~3個程度まで絞り込むように指示を出すのが望ましいです。そのうえで、(1)と同様に判断したうえで対応します。
学生に再検討をさせる時間が無い場合には、その場で教員が絞り込むことになります。その際は学生の個性やこれまでの学びの傾向、あるいは最近の社会トレンドなどを考慮して、可能な範囲の根拠をもって、(多少自信がなくても)「このテーマではどう?」と勧めることが大切です。
3) どのテーマも適切ではないと感じられる場合
残念ながら、示されたテーマがどれも適切でないという場合もあります。平凡であったり、解決策の提示が難しかったり、そもそもその学生にはふさわしくなかったり。そんな時には、その中からベストなものを選ぶのではなく、なぜどれもダメかを説明する必要があります。
時間があれば学生にテーマを改めて検討させたうえで、上の(1)(2)のプロセスに戻ります。時間がない場合には、学生から提示されたテーマ(すなわち学生自身の関心)に近いもので、かつ妥当だと思われるものを1つか2つ、「これがいいと思うよ」という形で例示するのが理想的な対応です。
教員が明示的に答えを与えることは重要ですが、同時に、学生に根拠を説明し、考えさせることも大切です。上の(1)(2)(3)に共通するのは、最終的には質問に対して教員がきちんと答えを出すということです。答えを曖昧にすると、学生が前向きにスピーチに取り組もうとする気持ちが崩れることがあるからです。
質問は学生との関係性を深める絶好のチャンス
学習者からの質問は常に歓迎されるべきものです。スピーチに関する質問を議論する過程で、より深くその学生の考え方やスピーチに対する向き合い方を知ることができるからです。
特に、綿密な指導が求められる学外大会に向けたスピーチ指導では、学生とのコミュニケーションがとても大切になります。学生から質問が来るということは、熱心さの表れです。どのような質問でも丁寧に検討し、明確な回答を返すことを心がけたいものです。
それでも、どうしても明快な回答が難しい時もあるでしょう。その時には、「よく考えたけれども、分からない」と答えることも必要です。これは決して教育を放棄することではなく、誠実に学生と向き合っていることの証でもあります。「分からない」と答えるとともに、解決に向けた方向を提示することができれば、その率直な助言によって学生の自立的学びを深めることもあるでしょう。
どのような質問でも前向きにとらえ、歓迎する気持ちで向き合うことができれば、スピーチで悩んでいる多くの学生を救うことができます。質問を通じた学生とのコミュニケーションから、学生の興味や関心と向き合い、彼らが自信を持ってスピーチに取り組めるよう、「言い切る指導」を実践してみてください。
▶ 関連記事:コンテストに挑戦する/しないの分岐点で学生の背中を押す [リンク]
▶ 関連記事:書きやすいスピーチのテーマは「見えるもの」を選ぶと驚くほど伝わる [リンク]

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など


