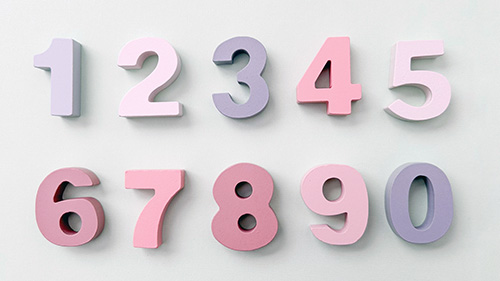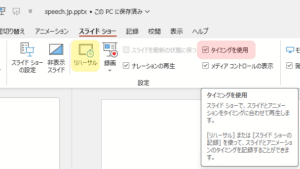数字データの印象操作は可能?「丸める/生/方向づけ」3種類の見せ方を知る
そのまま見せるか脚色するか、主張に沿った表現を。
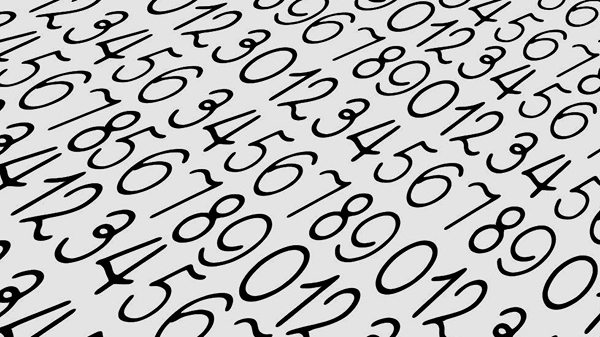
同じ数字でも、伝え方ひとつで印象は180度変わります。英語スピーチやプレゼンテーションにおける数字データは、客観的論証のための必須材料ですが、数字をどう見せるかによって、与える印象を変えることができます。大きく見せたいとき、小さく見せたいとき、あるいは正確さに意味があるときなど、いくつかのケースにぴったりの表現方法について考えましょう。
「数字は客観性が高い」というのは錯覚?
数字を用いた論証は、スピーチやプレゼンにおける「論理的な立証力(ロゴス)」の代表格です。数字は高い客観性を持つものですが、実はその数字の扱い方によって、話者の主張を支える力を向上させることができます。
たとえば「日本の人口」を尋ねられたとき、皆さんなら何と答えますか?「およそ1億2千万人」と回答すれば、多くの場合は正解です。でもこの数字をプレゼンで表現する場合に、以下のいずれでも「正解」であることに気づくでしょうか。
- It is about 120,000,000.
およそ1億2千万人です。 - It is 123,551,595. ※2025年1月(総務省統計局)
1億2,355万1,595人です。 - It is only about 120,000,000.
わずか約1億2千万人です。 - It is less than 130,000,000.
1億3千万人を下回っています。 - It is [more than / over] 120,000,000.
1億2千万人を[上回って/超えて]います。
お気づきの通り、数字は「伝え方」によって、そこから受ける印象が大きく変わります。これはスピーチにおけるレトリック(言葉を使って効果的に表現する修辞術)のひとつですが、数字には様々な「脚色」が可能であるということです。
こうして見てみれば、本来客観性が高いはずの数字データでも、実はそれを「大きく」も「小さく」も見せることができます。これは話者にとっては有利なテクニックですが、同時に聴衆にとっては「数字に騙されないこと」が重要であることを示唆しています。
スピーチで扱う数字は「丸める」のが基本
スピーチやプレゼンにおける「数字の見せ方のテクニック」には、主に「丸める」「生」「方向づけ」の3種類があります。
スピーチは、論文とは異なり、大きな数字の下一桁までを完全に再現することはほぼありません。多くの場合、"about"や"approximately" [約, およそ]といった言葉をつけて、数字を丸めて表現します。この「丸める」とは、四捨五入あるいは繰り上げ/切り捨てを意味し、この数的処理のことを英語でround (概数化)といいます。エクセルの「round関数」と同じ作用ですね。
スピーチで「およそ」という概数が好まれる理由は、複雑な数字を口にしても、長くて聴衆が瞬時に理解できないからです。冒頭のカコミの例①は一般的な概数表現ですが、1千万の位で数字を「丸める」処理をすることで、聴衆の理解を促しています。
カコミの例②は、日本の人口を正確な「生の数字」で表現したものです。これを口頭で言えば、"It is one hundred twenty-three million, five hundred fifty-one thousand, five hundred ninety-five."と長々と喋る必要があります。こんな長い数字を口頭で羅列されても、まず聴衆は理解できませんし、要するに「約1億2千万人」という概数すら把握してもらないリスクがあります。
数字を「生」で表現するのは、その詳細な一桁に意味がある場合のみです。たとえば、株価の変動を伝える際に「856円から924円に上昇しました」のように厳格な正確さが求められる場面がこれにあたります。
それでも、聴衆の理解を促す目的において数字を「丸める」のは、スピーチやプレゼンにおける基本的な数字データの処理方法です。これは、聴きやすさ、理解のしやすさへの配慮でもあります。
数字の「方向づけ」によって印象を操作する
上記カコミの例③④⑤の例は、数字に「方向づけ」をした例です。例③の"only"は、同じ数字でも「少なく理解されたい時」に使います。特に比較をする必要もなく、その数字の「少なさ」を強調できます。あたかもその数字が、現実よりも「下にあるかのような方向性」を印象づけられます。
カコミの例④の"less than"もonlyと同様ですが、than以降を基準点として、聴衆の印象を「下に向かう方向性」で操作しています。文脈によっては、"less than ~"の表現を使うだけで、「わずかしかないかのような印象」や「減り続けていく印象」を与えることも可能です。
カコミの例⑤の"more than"は、例③④とは逆に「上向きの方向性」を与える表現です。具体的に「どれだけmore thanなのか」には言及していないにもかかわらず、数の多さが強調される印象を与えます。例⑤の文章から受ける印象は、「1億2千万人を超える"大勢の人"がいる!」という文脈が感じ取れます。
スピーチで数字データを扱う際は、丸めるか、生で使うか、方向付けるかを都度考えることで、同じ数字が訴える意味が変わってきます。「前年比10%増の売上でした」と言うか「わずか10%増にとどまりました」と言うのでは、受け取る印象が違いますよね? プレゼンで登場する数字は、それぞれ自分が訴えたい文脈に沿った表現になっているかを確認しましょう。
客観的であるはずの数字データも、レトリックの力で方向(ベクトル)を与えることができます。ぜひ効果的に使って、説得力を高めてください。ただし、あまりやり過ぎると「わざとらしい誘導」に聞こえますので注意が必要です。レトリックには事実を捻じ曲げるほどの力はありませんが、真実をより効果的に伝えるための強力なツールです。ぜひ、戦略的に使ってみてください!
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など