【 辞世の句 】スピーチ最終段落の始まりと終わりに話者の魂を刻み込む
いよいよ終わる。その最後の言葉を残す覚悟を示す。
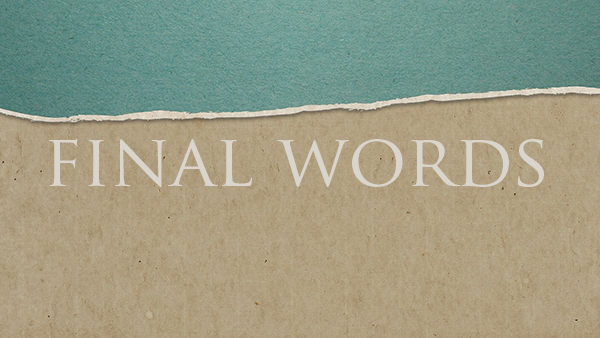
人生の最後、死を覚悟したときに残す言葉が「辞世の句」です。人生のすべてを凝縮したその言葉には、独特の重みと覚悟が宿ります。スピーチの最終段落もまた、話者の魂を刻む場所です。聴衆と真剣に向き合った証となる「最後の言葉」は、スピーチに重厚感を与えます。聴衆の心を揺さぶる「辞世の句」のような、最終段落の「始め方」と「終わり方」について考えてみましょう。
最終段落の「最初と最後の言葉」で思いを伝えきる
歴史上の偉人たちが遺した辞世の句には、彼らの思いの丈を端的に語る潔さがあります。短い言葉でありながら、重く深みのある響きを覚えるのは、そこに確固たる信念と覚悟が感じられるからです。多くの聴衆を相手に自分の信念を訴える説得型スピーチにも、当然にこの信念と覚悟が求められます。
偉人たちが命を懸けて詠む辞世の句と、わずか数分の英語スピーチの最後の言葉では、その重みは比較にならないかもしれません。しかし数分間という短い間ながら、スピーカーは聴衆と真剣に向き合い、問題を提起し、解決策を述べ、行動を呼びかけるのです。その証として、聴衆に最後の言葉を残すのが話者の矜持(きょうじ)であり、最終段落の大きな役割です。
4分程度の短いスピーチであれば最終段落は「結論」(conclusion)となるでしょう。8分程度のスピーチになると、最終段落の前の段落が結論となる場合も珍しくありません。いずれの場合にも共通するのは、最終段落の「始まり」と「終わり」の言葉の大切さ。それが対となって、スピーチにおける重厚な「辞世の句」を成します。
最終段落の「始まり」でスピーチの終わりを宣言
最終段落の最初の文章の役割は、「いよいよこれでスピーチが終わる」という雰囲気を示すことです。その最もシンプルな方法は、「このスピーチを通じて絶対に伝えたかったこと」を端的に言い切ることです。これには、「これを言わずして帰れない」というほどの最重要メッセージを、スピーチの最後で改めて繰り返す狙いもあります。
ここで話すべき内容は、最も重要な論点でも、最も象徴的な課題でも、最も重要な行動指針でも構いません。話者が大切だと思う点を、分かりやすい言葉で語ることが大切です。
たとえば、ジェンダー平等に関するスピーチであれば、"I say again, we must reconsider our attitudes toward gender equality" [改めて言います。私たちはジェンダー平等への姿勢を考え直す必要があります] のように、最も伝えたい内容を、覚悟を持って端的に「言い切る」ことです。
最後だからといって、難しい表現を使おうと思う必要はありません。もし具体的な表現に悩むようであれば、既に語った内容から「もっとも言いたいこと」が凝縮されている文章を探し、それを繰り返しすだけでも構いません。
スピーチが最終段落に至る頃には、メインの主張から解決策の提示までを既に完了し、後は最後のまとめをするだけという状況にあるはずです。その最終仕上として、辞世の句を詠むような話者の覚悟を、最終段落の「最初の言葉」で示すのです。そうすることで、自然と「いよいよスピーチが終わるんだ」という空気で会場を満たすことができます。
最終段落の「終わり」でスピーチのその先を感じさせる
最終段落の終わりの文章、まさに「スピーチ最後のメッセージ」は、スピーチ終了後に漂う雰囲気を決定づけます。スピーチでどのような「後味」を残すかは、この最後の言葉で決まります。後味とは、言い換えれば「スピーチが終わった後に、聴衆がどのような気持ちになるか」です。
スピーチ最後に登場する「終わりの言葉」を語るポイントは、スピーチを終えるにあたり「話者の心に秘めた思い」を端的な言葉で言い残すことです。真剣な空気を漂わせる。明るいトーンを描く。脅しの恐怖感で包む。問いかけで疑問を残す。これらはすべて「終わりの言葉」で決まります。
「話者の心に秘めた思い」を述べるということは、最後の最後に心の丈を聴衆と共有するということです。辞世の句のごとく覚悟を決めて、最後の思いをシンプルに綴れば、立派な締めの言葉になります。先にあげた4つのパターンを例に、締めの言葉を以下に示してみます。
- 真剣な空気を漂わせるとき:
Time is running out. [時間はもうありません。] - 明るいトーンを描くとき:
We can see a bright future, together. [ともに明るい未来が見えます。] - 脅しの恐怖感で包むとき:
This could be the final moment we spend together. [これが一緒に過ごす最後の瞬間かもしれません。] - 問いかけで疑問を残すとき:
Where will our destination be in 10 years? [10年後、私たちはどこに向かうのでしょう。]
このように、文章自体は簡単です。でもそれが意味するところの深さを感じられるでしょうか。話者がステージを去ったあと聴衆の心に残る空気感は、この「最後の言葉」によってつくられるのです。この効果を最大限に発揮するためにも、最後の言葉を言ったあとは、たっぷりと間(ま)を置いてから "Thank you." と言ってください。
最終段落では、「始まり」で論点を繰り返し、「終わり」で話者の心境を述べる。この基本を覚えておけば、スピーチ最後の雰囲気づくりで大きな失敗をすることはありません。辞世の句の潔さを再現しつつ、重厚で深みのあるエンディングを目指しましょう。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など




