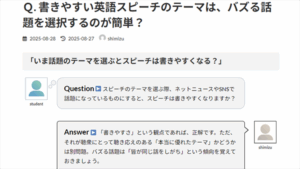伝わるスピーチは冷静に始まる。感情的なイントロが逆効果な理由とは?
イントロで感情を爆発させる話者に、聴衆はついていけない。

英語スピーチのイントロに、感情を入れすぎていませんか? 何とかイントロを印象的に演出したいという熱意は理解できますが、これは完全に逆効果です。特に、衝撃の事実を告白したり、感情的な呼びかけでスピーチを始める場合には要注意。聴衆は、話に引き込まれるどころか、極端な演出をする話者を見て「引いて」しまいます。
どのような話題でも、イントロは自然体の語りから。
英語スピーチの参考書を見ると、「イントロではお客さんが驚くような話をしましょう」というアドバイスが見られます。これ自体は間違いではありませんが、問題はその表現の仕方です。感情的な話をしたいのであれば、あえて冷静に語る余裕が必要だということを覚えておいてください。
元気だった友人の急逝、両親の離婚や家族の離散、同性愛のカミングアウトなど、聴衆のアテンションをひきつける話題をイントロに持ってくるパターンはよく見られます。そして多くの場合、そこには過剰な感情移入がみられることが多く、「話者が作りたい世界観」と「聴衆が受ける印象」に大きな開きが生じます。
「ショッキングな出来事で聴衆の注目を一気に集中させたい」という話者の狙いが成功するのは、それが本当に完璧な状態でデリバリーされた場合に限ります。言い換えれば、それは逆効果になるリスクが非常に高いやり方です。もし何らかの「感情的なオープニング」を設計している場合には、過度に感情的なデリバリーは避け、感情を抑えて語る方が安全です。
逸話よりも、その先の主張にこそ価値がある。
そもそも、スピーチコンテストは「衝撃的事実の披露会」ではありません。クラス発表のスピーチなら、例に挙げた「急逝・離婚・性的指向の告白」などは、それなりにインパクトがあるでしょう。でもそれが全国規模のコンテストとなれば、審査員はその手の話は何度も聞いていますから、今さら驚きはありません。
私がスピーチコンテストの審査員を担当する際にも、必ず何らかの"衝撃的な話"を演出するスピーカーに出会います。審査員にとっては、その"衝撃的な話"よりも、その事実を通じて「何を感じ、何を主張するのか」の方がはるかに大切です。その「主張」に、冒頭の"衝撃的な話"がしっかりと結びついていなければ、デリバリーは「やりすぎ」として減点になります。
音声審査(音声ファイル予選)では特に「やりすぎ」に注意!
この「やりすぎ」は、音声ファイルを提出する予選審査の際には、特に注意が必要です。音声審査では、当然ながら「声」だけが頼りです。その声に、過剰な感情移入を伴う演出を感じると、聞いている審査員の気持ちは一気に白けてしまいます。ひと言でいえば、話者の「誠実さ」やストーリーの「真実味」が感じられないのです。
極端なことを説明していると思われるかもしれませんが、数十本のスピーチを審査する予選会では、冒頭からサスペンスドラマのような震えた声で話したり、いきなり涙声で語り始めるスピーカーは存在します。本人は精一杯なので気付かないのかもしれません。応募前には、信頼する先生や友人に聞いてもらい、助言をもらうと良いでしょう。
イントロはスピーチの重要なパーツです。ぜひ一人の大人として、落ち着いた語りで聴衆を「話者の世界」に連れ出してください。目指すべきデリバリーとは「話者は落ち着いていても、聞き手は心が揺さぶられる」語りです。その第一歩として、まずは過剰な演出を手放してみましょう。
過剰な演出は、話者の信頼感(エトス)を失います。聴衆との一体感は、常に誠実な語りの上に成立する、というスピーチの鉄則を忘れないでください。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など