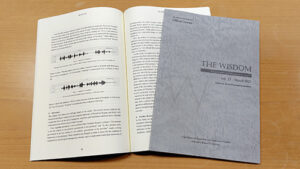Q. 英語スピーチのジェスチャーがぎこちないから恥ずかしい
「ジェスチャーがうまくいかず気持ちが落ち着きません」

Question ▶ スピーチやプレゼンではジェスチャーが大切だと聞きました。ジェスチャーのコツを調べて練習してみるのですが、どうしてもうまくいかず、ぎこちない動きになってしまいます。どうすればよいですか?
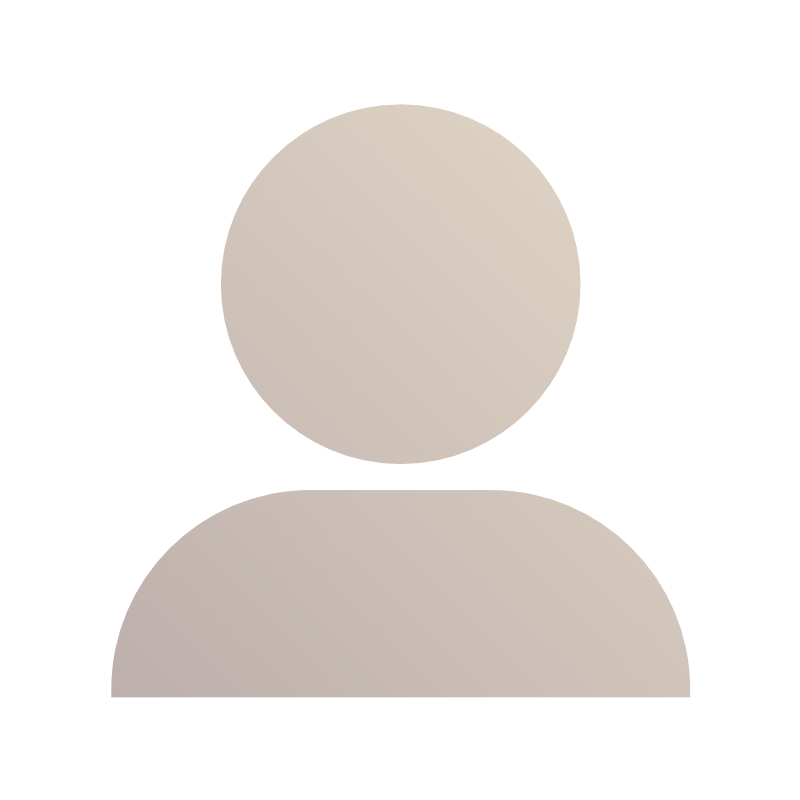
Answer ▶ 自分で納得がいかないうちは、ジェスチャーをつける必要はありません。本当に優れたジェスチャーは「後から思い出せないくらい自然なもの」です。難しければジェスチャーは使わず、その代わり誠実に気持ちを伝えることに徹するといいですよ。
ジェスチャーの本質的役割は「論点の強調」
ジェスチャーは必須ではありません。ジェスチャーはスピーチを構成する要素のひとつですが、すべてではありません。苦労してジェスチャーを練習するくらいなら、スピーカーとして誠実な語りを心がけ、視線や表情を磨くほうが何倍も効果的です。ジェスチャーの練習がストレスになる時は、とりあえず忘れておいて構いません。
憧れのスピーカーのジェスチャーを真似る人や、先生に言われた通りの動きを再現するのに精一杯の人がいます。前者はTEDスピーカーに憧れる大学生、後者は中学生や高校生に多いようです。それらが効果的であれば何ら問題ありませんが、とってつけたようなジェスチャーは、そのジェスチャーそのものに聴衆の意識が奪われてしまい、結果として重要なはずのメッセージが伝わりません。
ジェスチャーは、ここぞという場所で話者の大事な論点を際立たせるための道具にすぎません。いわば脇役です。仮にそれが「名脇役」であったとしてもスピーチの主役にはなりません。
優れたジェスチャーは「後から思い出せないもの」
意外かもしれませんが、弁論大会の審査においてジェスチャーはそれほど重要ではありません。やればやるほど加点されるわけではなく、逆に「適正ライン」を超えると減点(点数なし)です。適正ラインを満たす条件は、ジェスチャーの動きが自然で、かつタイミングも効果的であること。言うまでもなく、その逆はdistracting (気が散る)と審査用紙に記録されます。
本当に優れたジェスチャーを操るスピーカーだと、後からそのジェスチャーを思い出せません。それくらい自然です。慣れないジェスチャーと格闘するくらいなら、いっそのこと使わなくても大丈夫。ほとんどジェスチャーをしないスピーカーが、スピーチコンテストの全国大会で入賞することは珍しくありません。時折「入賞できなかった人の方がジェスチャーが印象的だった」といった声も聞かれますが、審査員はプロです。ジェスチャーが「脇役」であることを知っています。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など