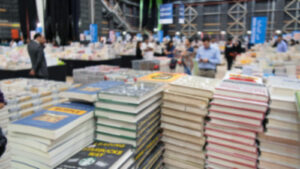英語スピーチやプレゼンテーションでは「起承転結」を避ける
転を省く"起-承-結"のリズムで「回り道せず結論へ」が基本形

日本語で物語を創作をする際のお手本的存在である「起承転結」。この4分割構造をそのまま英語に応用すると、途中で話題が逸脱した、論旨が迂回した、と指摘されることがあります。英語スピーチを学ぶ際には、書き起こしから最後の締めまで、くねくねと回り道せずストレートに論旨を運ぶ感覚に慣れましょう。
"by the way,"は、寄り道したまま帰らない危険フラグ。
日本語作文における「転」の役割は、(1)ストーリーに変化を起こし、(2)その変化を本題と結びつけて結論で締める、というものです。起承転結は絵本や四コマ漫画、落語、脚本にもみられるストーリー展開の基本として知られています。
一方、英語によるスピーチは、"転"を省くのが基本です。起-承-結のリズムは、「起承転結がお手本」と叩き込まれた日本人学習者には味気なく感じられるかもしれません。英語発表で"転"を省く理由は、全体を通じた論旨の流れを乱さないことにあります。
スピーチ中盤にさしかかり、上記(1)を狙って "By the way, ..." で新しいパラグラフを始め、(2)を目指して後続段落で本題との接合を図るスピーカーに出会うことがあります。その創造的取り組み自体は評価できるのですが、英語話者や専門家の観点から眺めると「なぜわざわざ自分から話を逸らすの?」という疑問が残ります。特に "by the way" は危険フラグで、人によっては寄り道したまま戻って来ません!
絵本も四コマ漫画も落語も脚本も、そもそも興味のない人は自分から見ることはありません。でもスピーチは違います。独演会でもない限り、あなたは多くの発表者のうちの一人にすぎません。みずから聴衆の集中力を欠きにいくような要素は排除し、ストレートで「逸れない話」を構成する配慮が必要です。
英語ライティングの段落はバトンをつなぐ感覚で書く
スピーチを書く時に心がけると良いのは、後続のパラグラフにバトンを渡す感覚をつかむことです。「起」の導入部(イントロ)でストーリーを起こしたら、あとは「承」(スピーチの本体)です。段落Aで起こした話題を段落Bに継承し、段落C、段落Dとつなぎ、話を展開していきます。
"承"の役割は様々ですが、たとえば具体の事例を挙げる際、本文では例1、例2、例3と、関連する「類似の配列」で挙げていきます。この時、話題を逸らさずにスムーズな流れを維持するコツは、リレーのバトンを渡すように、段落ごとの話題の受け渡しが無理なく成立しているかを確認することです。
仮に正反対の話題を持ち出す場合であっても、"転"のように新たな話題を意識させるのではなく、"In contrast," [それとは対照的に]や、"On the other hand,"[その一方で]のような表現を使って「先の話題の関連」として例示すると、それらは一貫した"承"の流れを保ちます。
起承結の基本は聴衆への配慮から生まれた工夫
突然の"転"は聴衆を動揺させます。お客さまにとっては、その"転"の話題が本題に戻るまで、元々の話を脳内に維持(retention)しておく必要があります。そんな負担をかけないよう、聴き手を意識した聞きやすさの配慮が「"転"を抜く」技術です。
ポンポンポンと心地よくパラグラフが流れていく感覚に慣れると、"転"の違和感が感じられるようになります。私の研究室では、スピーチの流れに違和感を感じたとき、「この話は毛色が違うよ」とか「ここから温度が変わるね」などと指摘し合います。"転"の感覚を意識すると、それを避けたり、あえて効果的に使ったりといった工夫ができます。
この"起承結"の3部構造は、スピーチ以外にも、英語でレポートや論文を書く「アカデミック・ライティング」の基本としても指導されています。英語圏で広く浸透しているコミュニケーション技術の基本として、覚えておいてください。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など