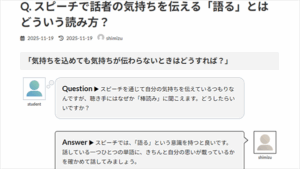スピーチコンテスト表彰式の審査員講評で「何を話すか」「どこまで話すか」
審査員講評の話し方と追加コメントで何を伝えるかの基本
※これは教員向け(教え方)の記事です。

教員がコンテスト審査員を務める機会は少なくありません。そもそも「審査員講評」では何を話せば良いのでしょうか。一般的な講評は、「(1)感謝→(2)総評→(3)助言→(4)激励」の4つのブロックを順に話せば無難にまとまります。とはいえ、ありきたりの美しい言葉よりも、「審査員からの率直なひと言」を付け加えることを心がけましょう。
どこまで審査員の言葉に耳を傾けてもらえるか?
審査員講評は、大会によって「受賞者表彰」の前の場合と後の場合があります。聴衆や出場者の気持ちになれば、結果発表の前なら講評よりも結果発表が気になりますし、結果発表の後なら、もはや「早く帰りたい」という心境かもしれません。どちらにしても、聴衆にとっての講評は、さほど「ありがたい時間」ではないと心得ておくことが大切です。
だからこそ、審査員の講評は「どこかで聞いたことのある美しいコメント」よりも、審査員が感じたままの率直な所見を伝える方がよっぽど意味のある時間になります。この本質をまずは覚えておくと良いでしょう。
とりあえずは、審査員講評にありがちな「4ブロックの無難な流れ」を以下に説明します。何を話せば良いかまったく分からない時の参考にしてください。
(1) 感謝:appreciaton
最初は大会関係者と出場者に対する感謝から入ります。感謝をする対象は、以下のようなパターンがあります。
- 審査員として招待された栄誉(全体向け)
- 円滑かつ厳粛な大会運営 (大会関係者向け)
- 本日の出場者やそのスピーチ (出場者向け)
- わざわざの来場ならびに応援 (観客向け)
(2) 総評:general impression & comments
感謝に続くのが大会の総評です。一般的には「レベルの高い素晴らしい大会」であったことを異なる角度から説明します。
- 〇〇大会にふさわしいハイレベルなコンテストだった
- どのスピーチも甲乙つけがたく素晴らしかった
- 最終的に受賞者を決めるのは非常に難航した
- 受賞者が限られていることを思うと心苦しい
といった話に続いて、全体に共通するスピーチの特徴的な印象に軽く触れておくと、次に触れる(特定の)「助言」が際立ちます。
(3) 改善に向けた助言:advice for improvements
総評に続くのが、「改善に向けた助言」です。1点か2点、審査員として出場者に伝えておきたい「具体的な改善点」を指摘するコメントです。
- 声が [小さすぎる/大きすぎる/不明瞭] だった
- (緊張のせいか)イントネーションが [一定すぎる/高ぶりすぎる] 傾向があった
- ジェスチャーが [多すぎる/少なすぎる/不自然な] 人がいた
- 全体に話すスピードが [遅すぎ/早すぎ/不安定] なのが気になった
- 解決策が [無い/不十分/不明確/多すぎる/少なすぎる] と感じた
「助言」ですから、ここは審査員が感じた率直な指摘を具体的に話すことが大切です。審査員としての経験と知見をもって「出場者が次のスピーチで即、改善できるヒントを伝える」という意識で話すとうまくまとまるはずです。
(4) 激励:encouragement
最後のブロックが「激励」です。出場者の今回の挑戦を称え、今後の成長を期待する言葉をかけます。同時に、大会の永続的な発展を願う言葉を述べるのも、クロージングの定番です。
- 今日の経験が必ず次の成功につながると確信している
- さらに素晴らしいスピーカーとなって再会することを願っている
- 皆さんの提案によってより良い社会になるに違いない
- 今大会が来年度も、またその次も、継続することを祈っている
どこまで本音で語るべきか?
上記の「(1)感謝→(2)総評→(3)助言→(4)激励」の流れは、いわば審査員講評の「鉄板」です。無難であることは間違いありませんし、審査員としてそのような言葉を期待されていることも確かです。一方これらの言葉は、聴き手からすればどこか「お世辞っぽく」「型どおりでありきたり」な講評と思われやすい側面があります。
ここで審査員を悩ませるのは「どこまで本音で語るべきか」です。「皆さん素晴らしくて審査が難しかった」という建前的な講評よりも、「どこが悪かったのか」「勝敗の決め手はズバリ何だったのか」を出場者は知りたがっていることを頭の隅に置いておくことは大切です。
清水が講評の機会を与えられた時には、(1)感謝や(2)総評は一旦忘れて、本質的な問題点や課題点の指摘から講評に入ることがあります。その理由は簡単で、そこにこそ審査員の講評の価値があると考えるからです。
ある全国大会本選では「もっと高いレベルのスピーチを期待してきましたが、今日は残念でした」と丁寧に本音を語ったこともあります。大変失礼な講評だったかもしれませんが、その言葉と、その講評に至った根拠(理由)の説明にこそ、審査員としての誠実さが表れると私は思うのです。
講評における「(1)感謝→(2)総評→(3)助言→(4)激励」は、極めて標準的な基本セットです。この形を守るのであれば、(3)の「助言」でぜひ審査員の本音に触れてみてください。審査員講評は、次の世代を育てる大切なひと言になります。どんな場面でも、出場者にとって有意義な言葉を伝えたいものです。
■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ
講演会・セミナー講師、
コンテスト審査員、執筆のご依頼など